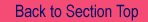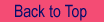ガーナ訪問記
ガーナ訪問記
榊原 洋一
人生はいたるところで偶然に支配されている。私がガーナに行くことになるなど、だれが想像しただろう。今回のガーナ行きの偶然のカードプレーヤーは、Dr.中村(安秀)である。国際医療計画学教室の飛び切りユニークな梅内教授が、だれか小児科の臨床のできる人をさがしている、という情報を聞いて、あの梅内先生とウマがあうのは、Dr.榊原しかいない、と直感したのだろう。Dr. 中村の人間関係の直感がはずれたことはない。ともかく、けた外れのキャラクターのDr.梅内と私は、本当にウマがあってしまった。ガーナ保健省の役人とのやり取りでも、いわゆる西洋風のマナーで梅内先生と対応しようとしても無駄である。前置きなどなしに、本当は何をしてほしいのか、何が不足しているのか、要点にずばりと切り込む梅内流交渉術は、相手側だけでなく同行した日本側のメンバーも含めた出席者をどきどきさせる迫力があった。
その梅内先生と、成田をあとにしたのは3月11日であった。「遠き落日」の野口英世が、アメリカを経由して日本の裏側のガーナに命懸けで出かけた今世紀初頭と今とでは、ガーナと日本の距離は比較にならないほど近くなっている。それでも、アフリカへは、ヨーロッパ大陸でいったん飛行機を乗り換えなければならない。12時間かけてたどり着いたロンドンから、さらに8時間サハラ上空を通過して、やっとたどり着くガーナのメンタルな距離はまだまだ東南アジアとくらべると遠い。
ガーナについての基礎知識は、まったく持ち合わせていなかった。チョコレートの産地であること、野口英世が黄熱病のワクチンの開発に失敗して、「I don't understand 」という本当に寂しく悔しい最期の言葉を残して亡くなった土地である、という程度であった。国勢についての統計をみると、人口1600万人、一人当りの年間国民所得400ドル、乳児死亡率1000人につき100人前後、主な産業は農業とほんの少しの鉱業、と書いてある。さらに現政権は軍事政権とあり、決して行く前から、心がうきうきするところではない。
アクラの空港についたのは、すでに熱帯の太陽が沈み、あたりが暗くなりかけた時刻であった。空港には銃をもった兵士がそこここに立っており、ガーナ政府が軍事政権であることを物語っていた。公用ビザのせいか、大して入国手続きには手間取らなかったが、概して係官の愛想は悪い。その国の民度と入国の際の手続きの厳重さは反比例する、という関係がここでも成立しているように思えた。平和民主国家の日本の玄関、成田空港のものものしい警戒振りと、入国審査官の固い表情を思い出した。空港の外で私たちを出迎えたのは、熱帯特有の生暖かいいろいろな匂いを含んだ大気と、頼んでもいないのに荷物に群がって運ぶ少年たちであった。今から約18年まえ、パキスタンのラワルピンジー空港で経験したのと同じ光景だ。JICAのKさんが、荷物をジープに積み込んでからチップを要求してくる少年たちに「おれは運んでくれって頼んでないぞ」と一言告げると、驚いたことにみな何も言わずに去ってゆくのである。ラワルピンジーでは、少年たちが動き出したジープのあとを走ってどこまでもついてきたのに、この国の少年はなんと素直なんだろう、と思った。そして、この印象はガーナ滞在中ずっとガーナ国民の一般的な印象になった。ホテルの従業員、病院の看護婦、道角で自動車相手にものを売る子供たち、皆明るく屈託のない笑い顔をしているのだ。西アフリカの住民の性格なのか、と思ったが、どうもそうではないらしい。隣国のナイジェリアの人は、一般的にもっと暗い表情をしていると複数の人が証言していることを考えると、別のファクターが関係していそうだ。ガーナ国内は、まだ時々部族間の争いはあるが、現在のローリング大統領が政権を掌握して以来大きな内紛はなく、若い国民は戦争を知らない世代である。そのことが彼等の「ハッピイスマイル」の原因だというのが大方の意見であった。
翌日から、分刻みのスケジュールで保健省の役人、WHO, UNISEF, USAIDなどの国際機関、そしてJICAが継続的に支援している野口研究所をめぐり、ガーナの保健医療、特に母子保健医療の現状について情報収集と意見の交換を行った。ガーナは熱帯雨森とサバンナ気候の中間に属するが、乾期のためか気温は35度を超えていても、東京の夏より過ごしやすい。頭の上に器用に荷物を乗せて背骨をしゃんとしてみちを歩いているガーナの女性に目を奪われながら、アクラ市内の各本部を回った。
保健省の役人は、「こういう人のことをエリートと言うのだな」と納得してしまうような、頭脳明晰な人ばかりだった。頭の回転と同時に口の回転も早く、ガーナの現状、問題点はすべてわかっています、といった様子であった。小児科病棟になれている私にとってさえみすぼらしく思える保健省の建物をみると、ガーナの最良のリソースは頭脳なんだ、と納得できた。かつて、日本も乏しい資源にもかかわらず、頭脳と勤勉な国民の努力でここまでこられたのだ、がんばれガーナ、と勝手にコールを送りながら、彼らと議論した。優秀な頭脳をもってしても、絶対的に不足している財源のもとで、どのようにして国民の健康増進をはかるか、という難問は解決できない。さらに、財源の多くを外国からの寄付にたよっているため、持続した財源を前提とする将来計画がたてられない、たとえたてても途中で頓挫するケースが多い、などいくら頭をつかっても解決できない問題に頭を悩ませていた。国際機関の行ったシュミレーションによると、現在の経済成長からみると、数十年後も最貧国にとどまっている可能性の高いガーナの若いエリートたちの悩みは深い。もっとも彼らに悩みを解決する方法がないわけではない。頭脳流出すればよいのである。これで少なくとも永遠に達成できそうもない目標を追い続ける、という悩みからは逃れられる。しかし、敢えてそれをしない彼等に明治初期の海外留学返りの日本人がオーバーラップする。
アクラ市内にあるガーナ最大の病院であるコレブ病院を訪れた。5〜6階建ての病棟が4つあるが、それぞれ内科、外科、小児科、産科の病棟であった。総人口の約半分が15歳以下という発展途上国に共通の医療事情がよく現われている。翻って日本では、小児科は斜陽だといわれ、公立病院では小児科病棟の閉鎖や定員削減があたりまえになっている。東大の「母子保健」学科も大学院大学の発足ともない「発達医科学」に変更されるという。たしかに聞こえはよいが、どのような名前で呼ぼうとも、世界中を見渡した場合圧倒的に必要とされている分野に対する、日本のコミットメントの姿勢が現われているような気がする。
たまたま勤務中であった小児科部長先生に病棟を案内してもらう。やや薄くらい大部屋には、肺炎、マラリア、下痢、悪性腫瘍とさまざまな疾患の小児が母親と一緒に入院していた。暗い部屋の中で黒い顔のなかに真っ白な歯が目立ったためか、明るい表情の母親が多い。看護婦は日本と異なり緑色の制服をつけてここそこに設けられたナースステーションで、どういうわけか暇そうにしていた。ナースステーションというより、看護婦のたまり場といったほうが適当かもしれない。一般的なケアは母親がやるため、看護婦の仕事はあまりないのだろうか?点滴の管理くらいが、彼女たちの仕事なのか、と不思議におもったが、実はコレブ病院だけではなく、その後見学した多くの保健所や病院でこの手持ち無沙汰の看護婦を見かけたのである。病院や薬品、医療スタッフの不足以上に、病気になったときに医療期間にかかる、という習慣がまだないことが、この国のプライマリーケアの問題点の一つなのだ。
アクラ市内のスラムに位置するアッシャークリニックでは、小児科の医師から次のような面白い話を聞いた。このクリニックでお産をしたお母さんでこどもの予防接種に来なかった人にアンケート調査を行った。予防接種に関する知識不足かと思い、予防接種の意味や、このクリニックで無料でできることを知らなかったのではないかと思って聞いてみたが、ほとんどそういうことは知っていたのだった。ではなぜ来なかったと問い詰めていった結果分かったことは、予防接種会場に着て行く新しい(母親の着る)服がなかったから、というのである。実はこれはこのクリニックのあるスラムに特異的なことではなく、ガーナ全国で見られる現象であると、あとで保健省のエリートの一人が認めていた。彼の説明では、初期の国際医療協力のミッションが、清潔の重要性を教えるために、乳児検診にはきれいな服装でいらっしゃい、と強調したことが、「清潔な服」→「新調した服」というように内容が変容していったというのである。その結果がガーナの予防接種率の低さになってはねかえっている。はしかなどは50%前後ときわめて低い憂うべき数字である。このことはたとえば、母親に対する健康知識のアンケート調査の結果の評価の際に陥りやすい誤りをよく示している。知っていることと、実際に実践することのあいだには大きな距離があるのである。
ガーナ第2の都市クマシの郊外にある平屋建てのヘルスセンターも、患者でごった返している姿を想像していたが、やはり看護婦が手持ち無沙汰にしており、患者数も一日30人前後とあまり利用されていない。簡単な外来手術ができるようにと、手術室の準備中であったが、がらんとしたセメント床の部屋の真ん中にほこりをかぶった中古の手術台がおかれているだけであった。「実は水道がないので、使えないのだ」とのこと。もし自分がガーナの医師であったら、がまんできただろうか、と自問した。
私たち日本の医師は、医学的に必要な治療はすべて行う、ことを前提として教育されてきた。目の前に患者さんがもし治らなければ、それは病気が現代の医療では治せない病気であるのか、あるいは私たちの治療法が間違っていたかのどちらかしかない。いずれにせよ、病気があれば現在最も効果があると思われる治療法を行うのが常識であり、かつ医師の勤めなのである。日本の乳児死亡率が世界で一番低いのは、なされるべきことがほとんどおこわれたためであり、それ以外の何者でもない、と私たちは信じている。言い方をかえると、治療とその効果はストレートな因果関係で結ばれている。しかし、ガーナでは治療と患者の間に大きな距離があり、治療と患者がうまくマッチしていないという現実があるのだ。日本で医療の向上といえば、そのほとんどが治療法の改善とリンクして捉えられている。しかし、ガーナではそもそも治療と患者がかみ合っていないのである。疲れる作業だが、まず治療と患者のマッチングを行うとこらから始めなくてはいけないのだ。患者の来ないヘルスセンター、水道のない手術室、1600万人の国民に対して700人とほぼ東大病院の医師と同数の医師しかいないマンパワー不足、どれをとっても、自分のやったことの結果を確認できる、閉じた回路のなかで仕事をしてきた私たちのこれまでの思考方法では、対応できない難題ばかりである。しかし、それが現在の地球の医療の姿なのだ。