

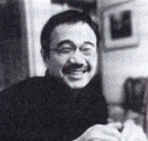
大きな書店の絵本コーナーを覗くと、眩しいくらい色鮮やかな絵本が目に飛び込んでくる。その中に、周囲の絵本とは趣を異にした柔らかで雅やかな雰囲気の漂う表紙の絵本「ごんぎつね」がある。
「ごんぎつね」は新美南吉の原作で、多くの人が小学生時代に読んでいるのではないだろうか。物語の挿し絵はそれぞれ読まれた年代により全く違うものだが、現在の「ごんぎつね」を見ると、昔からこの絵だったのでは?と錯覚してしまう。13年前から書店で発売されているものが、黒井健さんの絵本である。
黒井さんは、1947年新潟生まれの52歳である。イラストレーターとして26年、数々の絵本作品を描いている。その中で新美南吉の「ごんぎつね」と「てぶくろをかいに」は余りにも有名なのではないだろうか。また、かわいらしいふわふわの犬の「ころわんシリーズ」は、絵本好きの人ならば一度は目にしたことがあるのではないだろうか。宮沢賢治の「猫の事務所」や、賢治の詩を四季折々の景色の中の雲で表現している画集もある。
作品から、黒井さんのことを「素朴で土のにおいのイメージ」と勝手に想像していたのだが、初めてお会いして驚いたのはとても都会的な方だったことであった。
『僕は新潟大学教育学部中等美術科を卒業していますが、教師になるつもりは初めから全くなかったんです。本当はグラフィックデザインの勉強をしてデザイナーになろうと思っていました。横尾忠則さんや橋本治さんがデザイナーとして活躍を始めたばかりの頃で、デザイナーという職業が10代の僕にはキラキラしたイメージがあったんです。でも田舎に住んでいたのでデザインのテストの傾向と対策が全くわからなくて、一般の美術の勉強をして美大受験をしてやはり失敗してしまいました。一年おいて新潟大学を受験したんです。保育園から大学まで、自宅から徒歩15分で通えるような、長い間、家の近所で過ごしていたんですよ』
小学校の時から美術の成績が良かった黒井さんは「物を作ること」をとにかく得意としていた。美術、家庭科、作ることならどんなことでも夢中になっていた。
『子どもの頃は病気がちで、とても過保護に育ったんです。サラシの腹巻きをお腹が冷えないようにと母親に毎日巻いてもらった覚えがあります。僕の兄は生後5ヶ月のとき肺炎で亡くなってしまって、当たり前ですが母親は本当に後悔していたので、なんとか次の子からは丈夫に育てようと思ったんでしょうね。注意しすぎてかえって僕は身体が弱くなったのではないかと思うんですけどね。しょっちゅう学校も休んでいたんです。だから、家で絵を描いていることが多くてね。中学まで野球もやったことがなかったから、キャッチボールもできなかったんですよ。
痩せていてひょろっとしていて目立たない子だったんです。友達をいじめることもいじめられたこともなくて、おまけに意地悪されている子を助けたという記憶もなくてね。小学校の卒業式も中学の入学式も参加していないので、中学に行ったらクラスメートから「あいつはだれだ?」って見られてました。』
それほど目立たなかったけれど、黒井少年の作品は他の子どもたちを抜きん出ていたのである。小学5年のとき、設計図をおこしてボール紙と細い角材で金閣寺を作り、戦艦武蔵を作り、五重塔も作ったのである。欄干のところの卍組みまで丁寧に制作したのだった。
『だけど、せっかく作った金閣寺を焼いてしまったんですよ。二つ目の金閣寺を作ったからっていう理由と、当時僕はウルトラマンやゴジラに憧れていたので、そういうストーリーの中の炎上に憧れて焼いてしまったんでしょうね。何しろ、もし高校受験に失敗したら、円谷プロ(ウルトラマンの制作プロダクション)に就職しようと思っていたんですよ。だけどね、考えが変わったんですよ。よく考えてみたら、時間をかけて制作しても全部つぶされてしまうって悲しいですからね。
高校に入学できたから円谷プロ入社の夢はなくなったけれど、高校時代は妹の宿題をとりあげて相変わらず制作をしていたんです。「エッソスタンダード株式会社アリゾナ支社」なんていう物を作ったりしていました。そういうの、妹が作るわけがないんですけれどね』
それが高じて建築家にもなりたかった黒井さんだったが、学問としての美術の道へ進んでいったのである。
『教育学部美術科は、美術史はもちろんのこと、彫金、工作、デッサン、洋画、日本画、工芸とすべての美術をひと通り勉強するんです。自分にとっては大学は目的の場所ではなかったので、とにかく留年をしないで卒業しようと思っていました。ただ、結果的には非常に素晴らしい先生に出会ったと思いますね。主任教授はじめ、非常勤で来られている講師の先生はすべてプロの芸術家だったんです。ユニークな先生方でしたよ。自分にとって物を創っていくという憧れが生まれるようになったのはその先生方との出会いが大きかった。そのおかげで大学生活は面白かったです。漠然と物を創って行くんだという思いはあの大学生活から生まれたと言えるかもしれませんね。
授業を終わってから先生に飲みに連れてもらっていったり、一緒に東京まで展覧会に行ったりね。物を創る基本を、実際に創っている人たちから肌で感じて教わったと思うんです。
ある先生は一緒に連れ立って歩いていると、「おい、黒井。木が何か言ってるぞ。お前には聞こえないのか?」って。僕が「なんて言ってるんですか?」って聞くと、「自分で聞いてみろよ」って言うんです。自分で感じてみろということなんですよ。
そうかと思うと「おい、黒井。1ヶ月間、リンゴをどこかから持ってきて近くに置いてつき合ってみろ」って言われたんです。「でも先生、リンゴは見りゃわかるでしょ」って反発して、結局僕はやらなかったんですけどね。つまりその先生が言いたかったのは、リンゴでも石でもいいから、近くに置いてよく観察してみろっていうことだったんです。そのことはなんだかいつも心に引っかかっていましたよ。ずっと後になってこういうことを言いたかったのかなあってわかる瞬間があるんですよ。自然と忘れていた命題を思い出させてくれる瞬間っていうのが後からあるんです。
たぶん先生は、「その物」から受ける直感を感じさせようと思ったんでしょうね。直感っていうのは説明がつかないからね。直感っていうのはそこまでロマンティックなものではなくて、そのこと自体が重要なことなんですよね。その人自身が感じるものだから、その人そのものに他ならない・・・という意味なのではないかなってね。
自分の作品や人の作品について、言葉で説明していくのはアカデミズムに属した部分です。でもその素はただ直感じゃないかと思うんです。その作品を好きと思うか苦手と思うか。正しいとか間違っているっていうことではないんですよね。』
作品を言葉で説明するのはアカデミズムに属した部分・・・。同じ表現をすることの手段でも、絵を描くことと言葉で表現することの違いはなんだろうか。
『たとえば部屋の空間を文章で説明する場合と、絵で表現する場合。その素にある印象は同一だとします。ただ表現手段が違っているだけなんです。絵描きは本来言葉を使うものではないと言われればその通りなんですよ。文章で表現することと絵で表現することと、どちらもできる人もいますけれどね。
最も悲しいのは、自分の描いた作品を言葉で説明しなければならないときなんです。作品を見て、パッと「好き」と言われる方が嬉しい。「これはいったいどういう風に見たらいいんですか?」って言われるのは一番悲しいことです。何かを表現するというのは、基本的にコミュニケーションを持つということなんです。伝達手段なんです。だからそれが相手に伝わらないということは敗北になってしまうし、作品に対してひとつひとつ説明を求められるというのはとても辛いことなんです。
自分を表現する方法っていろいろあるでしょ。得手不得手って人それぞれ違うからね。ペンが良いか筆が良いか、だけどそれは本来同等なものなんですよね。
ただ、言葉で論理立てた方が、よりアカデミズムに通じるという利点はありますね。その世界で、他に対して説得力を持って偉くなっていく人は言葉の表現力も必要になってくるのかもしれません。
昔の画家たちがひとつの意欲と目的を持って創り上げた作品は、後世の美術評論家なり後世の知性が分類したものだと言えると思います。美術史が、そういうものですよね。学ぶ方はそれを教わって納得しているんですが、作品を描いた画家たちは同じ志だと思いながら「たまたまその時代」で創っていたのだと思うのです。作品や画家を位置づけをしたのはその後の知性なんです。その知性がなければそれらの作品は認められないと思うし、けれどもとても不思議でおかしな話でもあると思います』
絵本は、文章の説明を絵が成すのでも、絵の説明を文章が成すわけでもない。どちらも付け足しではないのである。もっと寄り添うように一体化して、むしろ映像のような世界が繰り広げられる。「ごんぎつね」は最初に文章があり、作者である新美さんは生存していないのだから、黒井さんが自分から新美南吉の世界に近づくしか方法はなかった。
『新美南吉さんという作家の生涯を、僕は今でこそ年譜の上で全て知っていますし、家族関係なども知っています。
けれども、ごんぎつねの絵を描くときには全く南吉さんのことを知らなかったんです。当時、絵を描くにあたってごんぎつねの話を読み直してみると、昔読んだときとは全く違った内容に思えたんです。昔読んだときは、ただのいたずらきつねの話だと思っていました。もう一度読むまでは、子供向けに可愛い絵を描こうと漠然と思っていました。しかし、もう一度きちんと読み返してみたら、これはいわゆる「絵本」ではないのかもしれないと思ったんです。今までの自分の手法では描けないと思って悩みました。全く手法が思い浮かばなくなってしまったんです。
とにかくどうしていいのかわからなかったので、南吉さんの生まれ育った場所、愛知県を訪ねてみようと思ったんです。それまで絵本を描くために取材をしたことは全くなかったんです。かわいい絵本ならば草花も近くに咲いているものを見ればすんでしまうし、図鑑を見て調べることもできる。でも「ごんぎつね」は、南吉さんの故郷の空気を吸ってみなければ描けないと思ったんです。その場所に行って2〜3日ただブラブラしていました。その場所に行ってみたら、ある種のインスピレーションがすとーんと入ってきたんです。それでもそのインスピレーションは全く具体的なものではなかったんです。
結局はどう描いていいのかわからないまま、おろおろと描き始めたんです。でも数枚描くとストップしてしまう。「ごんぎつね」はどちらかというとトーンの低い色あいで、それまで僕が描いていた絵本の明るいトーンとは全く違ったんです。だから描きながら(これでいいんだろうか・・・)ってずっと思っていて、何度もストップしながらやっと描きあげました。
しかし、発刊されてみるとどんどん売れたので、自分が思ったとおりに描けばいいと思う機会を与えてくれた本になったんです。それまで考えていた絵本のイメージを根底から崩してくれた作品になったんです。』
黒井さんの「ごんぎつね」や「てぶくろをかいに」の世界は、映像のようである。それはきっと建築家になりたかったという黒井さんの、舞台設定や景色の奥行き感などが確かなものだからかもしれない。背景の描き方や、登場人物のスポットや光の当たり方には、綿密な配慮やこだわりすら感じてしまう。
『僕が絵本を描くときは、一冊の絵本の中に、キャスティング・ロケハン・大道具・小道具・カメラアングルと、その全てを考えて制作するんです。もちろん映画にはかなわないですよね。けれどもやはり映画のように考えて制作します。それはね、僕の密かな楽しみなんですよ。実際の映画だったら、全てを自分だけでできるなんてないでしょ。僕は机の上の映画作りで十分なんです。
僕が作品制作するときは、頭で考えるよりも直感のほうが強いんです。ある大学の教育学部の美術理論の先生がご自分の研究のためのインタビューに来られたんですが、その方が「ごんぎつねの最後のシーンで、ごんが銃で撃たれて横たわっていて尻尾がすっと伸びているところに、ほんの少し重なるように兵十が立ちすくんでいますよね。それは黒井さんが、ごんと兵十の心が通じたことを表現されたんですよね」とおっしゃるんです。それを聞いて僕は「はあ〜、なるほど・・・」と感心していたんです。そうしたらその先生はとてもがっかりされましたよ。もしかしたら本能的にそう描いたかもしれないけれど、意図したかと言ったら全くしていなかったからです。
もちろん、意図して描く場合もありますけれどね。でも、なぜあの本が僕にとっていちばん大切かというと、敢えて意図しなかった本に初めて出会えたからです。こちらで伝えようと思っているし、わかってほしいと素直に思った作品なんです』
そして黒井さんの「ごんぎつね」は50万部も売れたのである。
『50万という数を考えたときにどれくらいの数か全く想像がつかないんです。でもどうやって想像するかというと、たとえばこの街に50万人の人口がいると考えて、その50万人の人たちが全員「ごんぎつね」を持っていると考えるわけです。そうすると、向こうのおばあちゃんからあそこの赤ちゃんまでみんなが持っているんだということになる。そんな風に考えると、本当にすごい!と思います。5万部・・だとしたら、東京ドームのお客さん全員が持っていることになる。実際考えると、とてつもなくすごい数字なんですよね。
そしてその喜びは、自由を得たようなものなんですよね。量をクリアしているということは、出版社は「黒井に頼んだらまた何か生まれるかもしれない」と誤解をしてくれるじゃないですか。ごんぎつねから学んだことは、いつも自分が納得の行く形で制作をしていこうということだったんです』
黒井さんは、自分の作品をどういう人たちに向けて制作しているのだろうか。
『実はね、自分に・・・なんです。それで良いのだろうかって疑問は持っていますけどね。でも、まず自分が楽しいと思わなければ作品を作るエネルギーが湧かないんです。「子どもたちのために描いていないの?」って聞かれることもあるけれど、子どもたちのために子どもたちに喜んでもらうために描いたことは実はあまりないんです。だって、子どもたちのため・・というほど僕は偉くないとも思うからね。でも自分の子どもを喜ばせるために描いたこともあるんですよ。子どもがでんぐり返しをするのが好きで「でんぐりでんぐり」という本を描いたこともあって、だけど本ができあがった頃にはすでに大きくなってしまって喜んでもらえなかったんですけれどね。
自分が楽しいと思っていることが人にも喜んでもらえたら、結局はそれがいちばんの幸せなんでしょうね』
淡々とそして飄々と話してくださる黒井さんは「ものを創ること」について大げさに表現しない。他人の感性に対してなにかを強要することについての細心さをおそらく子どもの頃から持ち続けているのだろう。黒井さんの持っている「自分のために創る喜び」は、他人を喜ばせたいという気持ちの通過点を越えなければ心底からは得られないようなそんな気がしてならなかった。
『フリーの仕事は良いですね・・と、たまに言われることがあるけれど、僕は「商品」を作っているから結局は経済社会と通じている。けれども会社勤めの人と何が違うかと言われたら、お金の流れが1カ所からか数カ所からかの違いなんです。ある意味、こういう立場はわがままかもしれない。けれどもわがままさというのは僕たちの仕事では大切なのかもしれないんです。良い見方をすれば、わがままさは「自分はこういうものを創りたい」という熱意があるからこそ持つものなんです。その意志を通すエネルギーを持ち続けるのは容易なことではない。僕の場合は、目の前の仕事を仕上げるにあたって自分の心の底にあるエネルギーを見つめて、意志を通すエネルギーがある!と思うときとそうでもないときがあるんです。そしてそのエネルギーはほんの小さな灯りでしかないこともある。作品に出会ったり、依頼者に会ったりして、そのときの一瞬に何かを感じることがある。そうかと思うと、作品とずっとつき合っていくうちに少しずつ自分にとって大切なものになっていくこともある。それは人間関係と似ているんですよね。その灯りが小さくてもともっていればその仕事に関っていこうと思うんです』
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
『他人といて楽しい人と、ひとりでいて楽しい人と、二通りだと思うんです。ある画家さんのエッセイに「アトリエで絵を描いていると無性に人恋しくなるから、外に出て人に声をかけて飲んだり食べたり騒いだりしていると3日もしていると煩わしくなる。それでまたアトリエに入る」という繰り返しをしていると書いてあったんですよ。ひとりがいいのかっていうとそうでもないし、人といるのが煩わしいこともある。孤独と自由は常に同居してる。自由であるということは束縛を受けないということだけど、孤独ともつき合わなければいけないでしょう。じゃあ、どちらが比較的居心地がいいかっていう目盛りの分量は人それぞれなんですよね。だから両方のどちらかを無理して選ばなくてもいいんじゃない?って思うんですよ。人恋しいときは人に会って、人に疲れたら一人になって・・・そういうのを繰り返していいと思うんです。他人と一緒にいられないことを嘆くこともないし、みんな、人間関係で悩んでしまったりするでしょ。親子関係でも夫婦関係でも、人間関係ってそうだと思うんですよ。でもあんまり「こうあらねばならない・・・」っていう方向に考えないほうがいいんじゃないかなって思う。どっちも貴方で、どっちも私って受け止めたほうがいいんだよね。いわゆる「一般」に属さなければ異常なんだと思ってしまう恐さ、そういうことが世の中に浸透しすぎてるんですよね』
(インタビュアー 三上敦子)2000.3
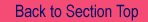
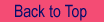
Edited by Atsuko Mikami