


アジアの熱帯林、亜寒帯の森、オセアニアの草原、中央アジアの高地、アマゾンの密林、日本の山里。
よこはま動物園ズーラシアは、地球上の様々な環境とそこに生息する野生動物が一体化するような、今までに見たことのない動物園である。世界的に希少な動物を含めて60種の動物を飼育し、オカピやインドライオンは日本で初めて繁殖に成功した。また血統管理や累代繁殖、生態研究も行って成果をあげている。
よこはま動物園は4年前に開園し、女性園長が就任した。増井光子さんは動物園勤務の大ベテランで、井の頭自然文化園、多摩動物公園、上野動物園で獣医師として、また園長として、長い間勤務されてきた。
無類の動物好きで、動物と共に歩んできた増井さんのお話を伺ってみようと思う。
* * * * * * * * * *
『物心ついたころから、動物が好きでした。虫でも魚でもなんでも。私が育ったのは、間もなく第二次世界大戦を迎えるという時代だったので、今のようにペットとして動物を飼う人はそういませんでした。夕方になるとコウモリがたくさん飛んでいて、ネズミはどの家の天井裏でも走っていて、大阪市内でも、そのネズミを食べにヘビも潜り込んできました。そんな風に小動物が身の回りにたくさんいたのです。
私は大阪市に小学校2年まで住んでいました。戦争がひどくなってきたので奈良県境の生駒山麓の村に疎開したのですが、疎開した先は、東は生駒山、西は延々と続く水田で、私にとっては絶好の遊び場でした。
おもちゃもあまりなかったので、ナイフを使って竹とんぼを作ったり、缶けりをしたり、天気がよければ魚とりをしたりと、いつでも野山を走り回っていました。
幼稚園のころは魚屋さんにいるドジョウやウナギを見ていることが大好きだったのです。昔は切り身ではなくて、浜に朝一番で上がった新鮮な季節の魚が店先に並んでいたので、私にとってはまるで水族館みたいでした。
小学校5年の時に、はじめて犬を飼って、犬くらい可愛い動物はいないんじゃないかと思うようになりました。テリア系の雑種で、「アカ」という名前をつけていたのですが、山に行くにも川に行くのも何処に行くのも一緒でした。アカも含めて子ども集団で、みんな元気で、動物と人が一体になっているような感じでした。
アカが大人になって子どもを産むようになり、犬の繁殖に興味を持つようになったのです。遺伝的傾向がどうこうとか、血統書の見方はどう見るとか、そういうことにも興味が出てきました。
そうしているうちに、一般の人が好む犬というのをだんだんわかってきたんです。例えば、日本人はやはり日本犬が好きなのです。雑多な子どもを作るよりも、日本犬らしい犬を作るほうが引き取り手がある。でも日本犬にするためには、純粋な系統を持っていなければダメでした。アカは雑種だったので、どういう子どもができるかわからない。いくらオス犬に日本犬タイプを選んだとしても、生まれてくる子どもは保証ができないんです。そんなことをしていたら、犬にも好みがあるということがわかってきました。この犬とこの犬を交配させてみたいなあと私が思っても、犬同士はお気に召さないとか、そういうこともわかってきました。犬も考えを持って生きていることがわかって、犬の行動を観察することが面白くなりました。
純粋犬の繁殖というのは、一般的に犬の好みというものを人間は考慮しません。このチャンピオンとこのチャンピオンを掛ければチャンピオンができるというように、犬の好みは無視して半ば強制的に交配させる。でも、自然に暮らしている動物にはちゃんと考えがあるんだなあということが、このときわかったのです。
中学から高校にかけては、紀州犬を作り出すにはどうすればいいかということを考えました。犬仲間の先輩にいろいろ話を聞き、形だけは整えることができても、精神構造まで理想の犬を作るとなると大変だということもわかりました。
形も気性もしっかりした犬を作りたいという風に考えると、餌だけでなく、運動も考えなければいけない。餌のことを考えたりすると、犬の栄養学や生理学もよく勉強しなければなりません。この食べ物が好きだからと言って、そればかり食べさせていたら栄養状態に悪いとか、運動させなければ筋肉が丈夫にならないとか、ずいぶんいろいろなことを勉強し、実行しました』
増井さんは動物のことを何でも知りたいから、とにかく動物に関する本は手当たり次第に読んだ。彫刻や絵画などの芸術や、化石、恐竜という古生物学にも、とても興味を持った。知りたいことを片っ端から調べると、思いの外、いろいろなことが関係していることを知るようになる。興味を持つ全てが、動物のことを知りたいということに尽きるのだった。そして気がつくと、獣医師になりたいと思うようになっていた。
『獣医学というのは大変に幅が広くて、動物学、動物解剖学、動物行動学などの動物に関するあらゆることが関わっているのです。それに加えて、外科や内科の臨床医学を学ぶわけです。普通の学問では動物を外から見ているだけなので、内臓の仕組みがどうなっているか、生理や骨組みはどうなっているか、というところまではいかないのです。でも獣医学はそれをしなければ手術もできないし、全てを知らなければならない。そこが私にとっては大いに魅力でした。
動物を訓練することも楽しそうだなと思ったし、動物画家にもなりたいと思ったけれど、でも骨ごと知らなければ描くこともできない。部活も生物部でしたから動物一筋でした。
麻布獣医科大学を受験したのは、学校に歴史もあったし、当時の学長の板垣先生が日本犬保存会を作ったメンバーの一人だったということもありました。私は高校時代に紀州犬を飼っていて、日本犬保存運動にも参加していたのです』
可愛がっていたアカは、増井さんが中学2年の時に死んでしまった。その後、高校生になってから飼い始めた紀州犬を連れて上京し、大学生活を過ごすことになった。獣医師になることに大きく近づいた増井さんは、動物園で働きたいと心の中で決めていたのである。それには、キリンやゾウのような大動物の世話ができなければと思い、馬術部に入部し、乗馬以上に厩舎作業のほうを徹底した。そして就職が近づく頃、動物園実習をすることになった。
『動物園に実習に行ったのは、その頃、女性では私が初めてだったようです。最初は猛獣舎で、トラを担当しました。係の人に着いて、飼育実習と獣医実習を40日間したのですが、それでますます、動物園で働きたいという気持ちが募りました。
就職活動をするにあたっては上野動物園に直接お願いに行ったのですが、上野動物園は東京都の管轄なんて知らなかったのです。「ここは都の施設だから、定員や、枠があって・・・」と、いろいろ説明されました。結局、「1年間は臨時職員としては働かせてあげるけれど、将来は保証はできませんよ」と言われました。でも、もう就職できたようなつもりで、嬉しくてね。仕事を初めたら、楽しくて楽しくて、動物園で働いてあらゆる動物を診ることが本当に楽しかったのです。
ただ、獣医師は動物に嫌がられますね。飼育係の人には世話をしてもらえるから馴れますが、獣医師は痛いことをするし、薬品の匂いが染みついていますからね。タクシーに乗ると、「清掃局の方ですか?」と言われたことがあります。自分では気付かないけれど、身体に消毒薬の匂いがしみついているんでしょうね。動物は敏感だからそれがわかるようで、白衣を着ないで行ってもわかってしまうのです』
増井さんはこれまでに数々の動物園を見てきた。どの動物園にもそれぞれに異なった目的や特色がある。
『上野動物園、多摩動物公園や井の頭自然文化園と三つの施設を体験しましたが、全てが持ち味が違います。上野は都市型の動物園なので、標本的に数多くの動物を見られるようにしている。多摩は種類数は少ないけれど、群で飼うことで野生に近づけている。井の頭は日本産の動物を中心にして、ニホンリスの森構想とか、井の頭池にオシドリをたくさん放そうという独自の展示方法を展開している。どの動物園もそれぞれの特徴があるのです。
ここ、よこはま動物園では、環境展示、生態展示が特徴で、植物と動物を一体化させているのです。動物舎の中に植物を一緒に入れていることで、森のような雰囲気を出している。園内の東南アジアの地域では椰子の木を植えていて、雰囲気づくりにも努力しています。
散歩に最適のようで、レギュラーゲストが多く、4割くらいは何度も通ってくださるゲストです。動物園は子どもだけのものではなくて、大人も楽しめるということで、ここには大人のゲストが大変多いのです。森林浴のような気分になって気持ちがいいという意見が多いんですね。動物園の要望も時代と共に変化するので、自然がまだ豊かだった今から30年以上前にこういう場所を作っても流行らなかったと思うのですが、自然への欲求の強い現在にはマッチしていると思われます。
でも、上野動物園のようにたくさんの動物を次から次に展示しているところに馴れている人からは、「よこはま動物園では、動物が隠れていて見えない」とオープン当時はそういう苦情もありました。でも、その苦情も次第に少なくなり、今では9割の人にまた来たいと言っていただいています。
6月初めの霧雨が降っているときに園内を歩くと、「うわっ、きれいだなあ」とつくづく思うのです。若葉や青葉が緑の濃淡をつくり、しっとりと木々が濡れていて、そういうときに「日本の緑もなかなかのものだなあ」と思います。都会に住んでいる人はそういうのを求めているんじゃないかなあって。
山や海はもちろんいいけれど、体力や時間がないと気軽には行けませんよね。でもこういった公園というのは気軽に歩けるので、身体が弱い方でも楽に散歩できますからね。ここで体力をつけていただいて、それから自然の中を歩くのもいいのではないでしょうか。
幼い頃は、ふれあい動物園のように、うさぎなどの小動物を触ったりするところ。少し大きくなったら大きな動物を見られる所。そして更に自然に関心を持った子は、中学・高校になって本当の自然の中に出ていくようにする。そういうのがいいと思うのです』
いろいろお話を伺っていると、園内の向こうの山のほうに、ゾウが人を乗せてゆっくりと歩いているのが見える。運動中なのだろうか。一瞬、ここは何処だろうと思ってしまうくらい木々に囲まれている。
『私は、アロマテラピーとか、バイブレーションとかに関心があるのですが、森林浴はアロマテラピーみたいなものですよね。そのせいか、この動物園は、とても繁殖率がいいのです。なかなか生まれにくいものが生まれたりしています。例えば、ドールという赤色のオオカミの仲間がいますが、増えているのはここだけなのです。それからウンピョウというヒョウの仲間も、とてもよく育っています。植物の生い茂る中で遊んで枝を囓ったりしているうちに植物のエキスを体内に取り込み、それが動物のホルモン系にうまく働いているのではと推測しています。その代わり、動物たちは植物をよく囓ったり飛びついたりするので、植物はぼろぼろになっていきますから、植物管理が大変です。でも、植物あっての動物だということもよくわかるようになりました。
それから、川のせせらぎ、風の音、音楽とも言えないようなバイブレーションがどれだけ生態に影響を与えるか、ということも一層感じるようになりました。音も動物にとっては非常に大切なんですね。だからここで音楽会もやってみたいのです。動物園で音楽会なんていうと、動物が驚くなんていう人もいるけれど、動物も音楽はわかりますから。例えば、馬の調教に民謡を使ったりすることもあります。馬を訓練するときに、トレーナーが民謡をかけながらトレーニングすると、歩くリズムに合っているらしくて馬がとても歩きやすいようです。またトレーナーにとっても、いいのです。教えていて馬の覚えが悪いと、つい人間がかっとなってしまう。でも音楽をかけながらやると、人間もゆったりとして、馬に当たらなくて済むとトレーナーから聞きました。
風に葉がざわめく音、そこに匂いのアロマがあり、それが動物や人にいい作用をしているのではないかと、この動物園にいると感じます。たぶん私がずっと自然の中で過ごしてきたから、わかるのかもしれません。自然の中で暮らした経験のある人なら、誰もが感じられることなのでしょうね』
増井さんは、アフリカや東南アジアや世界のあちこちを旅行してきた。何処に行っても、日本の森林は素晴らしいと思うそうだ。外国の素晴らしいところは、動物の力を借りて暮らすことが多いことだという。
『オーストラリアでは、牛が広いところで放牧されていますが、牛を一カ所に集めるときはカウボーイが馬を使って集めているのです。羊の群は、牧羊犬が集め、空港に行けば麻薬捜査をするために犬が働く。日本では、牛や馬が働いている姿をあまり見なくなってしまったし、牧羊犬というのも見たことがないですね。外国の動物は自分の役割をよく知っているので、おとなしいのです。働くことのほとんどない日本の犬などはストレスが溜まっているのか、神経質で我が儘になっているような気がします。今の日本はあまりにも機械の力を頼りすぎていますね。日本人は潔癖すぎるのかもしれないです。
外国で乗馬をすると、現地の小学生が大人たちをガイドすることもあります。一日に80キロ以上を馬で走るレースがあって、ビギナーのうちは誰かに先導してもらわないといけないのですが、9歳の男の子が日本人の大人たちのガイドしているのを見ました。自然の中を標識だけを頼りに80キロの道を進むのですが、午後3時にスタートして、午後11時の真っ暗なところを帰ってきました。9歳といっても、もちろん乗馬の技術はありますが、それでもひとりで大人たちを先導するのはすごいことだと思います。ひとりで、大人達を連れて戻ってこなければいけないという責任を持たせられている。「指示待ち」なんていう子どもは、そういう土地にはいないでしょうね。野外に入ったら自分で道を切り開いていかなければいけないわけですから、人間も強くなると思います』
増井さんは、日本の子どもたちにどういうことを望んでいるのだろうか。
『子どもの頃って随分、残酷なことをしてしまいますよね。トンボの羽をむしったり、虫を殺したりね。だけど、やがて、皆、そんなことは卒業していきます。昆虫採集ってこどものうちはみんなやるでしょう。捕りたいという衝動を抑えられませんよね。私は、子どものうちは、どんどん虫や魚と遊んだほうがいいと思います。「虫を殺してはいけない」なんて抑えてしまうことが、いいのかどうか、わからないです。
子どもの頃に、たくさんの虫を捕ってきてしまったら、こうやれば死んでしまうということは嫌になるくらいわかります。代償と言うと、代わりになった動物たちには本当に申し訳ないけれど、種という単位でみると昆虫類の再生力はすごいです。でも今の子は、ほとんどそういうことをして過ごさなくなっている。それで、人を殺してみたかったなんて言って、人を殺しちゃったりすることもあるでしょう。昔は、喧嘩のあげくに怪我をさせてしまうことはあっても、人を殺してみたいと思うことはなかったと思う。ある幼児期に、虫を殺したりして、殺生ということに対して卒業していると思うのです。そのために、いっぱい虫に刺されて、自分も痛い思いをする。それが普通の生物学的な成長ではないかなあと思うのです。
昆虫採集よりも、環境破壊のほうがもっと大きな影響を与えると思うのです。昆虫はものすごい勢いで増えます。増えたものを誰かが歯止めをかけなければ、世界中が虫だらけになってしまいます。でも増えたって、それを餌にしている生き物もいる。蝶にしてもトンボにしても何千、何万の卵を産んでも、わずか数匹が親として生き残ってくれればいいのです。後はみんな他の生物のために子孫を蒔いているようなものです。そしてその虫のおかげで生き長らえているもう少し大きな動物がいて、そしてその動物も誰かの餌になっている。こうして生物界は持ちつ持たれつの関係になっている。
生物が増える場所を根こそぎダメにしておいて、子どもがやりたいという昆虫採集を禁止するのは、本末転倒ではないかと思うのです。子どもが採る昆虫の数なんて、大したことはないのですから。
今、日本の国が乾燥しつつありますよね。昔は、瑞穂の国と言って、水田が多かったのに、今は休耕田が増えて、かちかちに地面が乾いてしまって、水の面積が減ってしまっています。その乾田化してしまったところに水を張れば、あっという間に虫が集まってきます。そうやって環境さえ整えれば、カエル採りやトンボ採りが出来るようなところになっていくのです。現在のような環境の中で子どもが育っていったら、蚊に刺されても反応がひどくて熱を出して大騒ぎなんていうことになってしまう。あまりにも無菌的なところで暮らしたら、人間はそうなっていってしまうのではないでしょうか』
たくさんの昆虫を捕まえて、飼ってみたり、遊んでみたり。そして犬やネコから始まって、もっともっと大きな動物を見るようになった増井さんだからこその次の話は、何よりも感動してしまった。
『魚にだって表情があると思うのです。魚は表情筋が発達していないから、関心のない人が魚を見てもどれも同じに見える。でも魚も感情の動きが表出されないだけで、彼らは彼らなりに表現方法があると思うのです。それは、毎日、関心を持って観察している人でなければわからない。飼っている人の足音や声の震動音もわかると思うのです。
水族館でイシダイに芸をさせることがありますが、その中に、箱の中に問題が入っていてイシダイが箱の蓋を開けて問題を解くというショーがありました。ある時、その箱をイシダイがいつものようにつついても開かなかったそうです。そこでどうしたかというと、イシダイはその箱を噛み破って、中の問題を取り出し、先へ進んだという例があります。そういう機転の効き方は、イシダイの大脳発達状態からすればとても理論的には考えられないことなのです。彼らは、マッチ棒の先くらいの脳味噌しかないんですから。フタが開かなければ、いつまでもグルグルと箱の周りを回るか、あきらめてしまうか、どちらかしかないのが普通なのです。それなのに、フタが開かなければ噛み破って中の問題を取り出そうとした。それは、ある種、思考をしているということになる。そしてそれは、とても大変なことなのです。
クモだって学習をします。亡くなった児童文学者の人の観察していたクモなのですが、庭に大きなクモが巣をかけたので、あるとき、なんの気なしにお刺身を巣にかけてみたら、クモが虫と同じように食べたので、それでおもしろくなって、いろいろなお刺身をかけてみたそうです。最初のうちは、お刺身をかけて巣をゆすったりして合図を送ると、クモがさっと現れて、糸を巻き付けて食べていた。そのうちに、そのお刺身は死んでいるものだということがわかったから、糸を巻きつけずに食べるようになった。クモみたいな無脊椎動物でもきちんとそういうことを学習するんですよね。
植物にだって、毎日「キレイだねえ」って声をかけてやると長持ちするっていうでしょう。切り花だって、そうなんですよね。それはやはり、人の声の調子とかがちゃんと伝わっているからだと思います。生き物というのは、みんなそうだと思うのです。
そしてそれは、いかにその人が対象物に対して、関心を持っているかどうかなのです。すごく関心を持っていて相手の行動を読み切れれば、それは相手に通じます。外国の動物園でキングコブラを飼っている飼育係の人で、コブラに平気で触れる人がいました。コブラは決してその人に攻撃を仕掛けたりしなかったそうです。それはコブラのほうも、その係を観察し、双方がお互いを理解し合っていたからではないでしょうか。
上野動物園のゾウガメの飼育係の人もゾウガメの顔つきは一匹一匹違うと言っていました。毎日、観察している人にはそれがよくわかるのです。
イソギンチャクのような無脊椎動物だって、飼っている人には様子がわかる。でも、関心がなければ全くわからない。ただの物体になってしまうのです』
* * * * * * * * *
『獣医師になる。動物園で働く。小さい頃にやっていた犬の系統繁殖は、動物園で今まさにやっている種の保存に役立っている。馬術部に入ったのも、動物園で働きたかったから。乗るよりも作業のほうをいっぱいやりました。でも、実際に動物園で働いたら、馬術部の作業よりもずっと楽だったのです。寝藁を干したり、餌の草刈りも馬術部ではやっていましたけど、動物園では餌を入り口まで運んでくれるのですからね。野生動物を追いかけるためには走ることも必要だと思って、マラソンもやっていました。
私は本当に幸せ者で、夢がほとんど叶っているのです。寄り道してきたことが全て役に立ってきました。寄り道することを無駄と思うか、いつか人生の中で役に立つと思うか、考え方次第だと思うのです。
そして、何処でも眠れて、何でも食べられる。人間が気楽にできているのかもしれませんね。子どもの頃から気楽だったように思います。あまり人のことが気にならないのです。人がなんて言おうが、全然耳に入ってこない。どう思われているかなんて、気にしたこともない。人と比べる自分がないから幸せなのかもしれません。きれいな服を着たいとか、美味しい物を食べたいなんていうことも思わない。
もしかしたら、いつまでも子どものままなのかもしれないですね』
お話を伺っていて、増井さんと一緒にどんどん気持ちが高揚していく。いつまでも追う夢がある人は、あんまり見たことのないような、どこまでも真っ直ぐに突き抜けている光みたいなものが見える。人の「明るさ」っていうのは、朗らかさとか笑顔という見かけではなくて、こういうことを指しているんじゃないかなと実感した時間だった。
もしかしたら・・・と思って、さらなる夢を聞いてみた。
『大それた夢なのですけれど、オリンピック選手になりたいのです。エンデュランス競技といって、馬に乗って決められた時間内に80キロ以上の距離を完走するという耐久走の競技があるのです。2年前から日本でも公認競技になったのですが、外国では以前から60カ国で公認競技になっていて、それが北京オリンピックでは正式種目になるだろうと言われています。エンデュランス競技は、まだ選手層が薄いので、今がチャンスなんです。馬術競技というのは、年齢も性別も全く関係がなく一緒に競技をしますが、選手寿命が長いのが特長です。86歳で耐久走の世界選手権に出られた方がいたり、イタリアでも60歳以上でオリンピックの競技に出られた方がいます。だから、「まだまだ私にも可能性がある!」って思ったのです。エンデュランス競技は、馬に乗ってマラソンをやるようなもの。私のためにあるような競技じゃないかって思いました。この競技が日本で行われるのを、20年近く、待っていた甲斐がありました。出場するためには、外国の競技に出てポイントを獲得してこなければいけないので、今年からそれを始めようとしています。もし出場できたら、北京大会のときに私は71歳。日本のスポーツ史上最高齢のオリンピック選手になれるかな?!』(インタビュアー 三上敦子)02.7.1
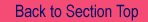
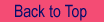
Edited by Atsuko Mikami