


学生時代に、時々、テレビで拝見する森毅先生は、とても印象深かった。肩書きとかそういうものから受ける雰囲気ではなくて、(この人は普通の人じゃない)と感じられる存在感があった。それから、たぶん中学生向きに書かれた「間違ったっていいじゃないか」という、先生の著書を知って読み進むうちに、もやもやと霧の中にいるような胸の内がぱあっと晴れ渡るような気分になったことを今でも覚えている。
森先生に実際にお会いしてみると、笑顔が何よりも印象的で、とにかくお話がとても愉快。失礼と思いながらも、込み上げてくる笑いを抑えることができなかった。その緩やかな人柄がこちらの肩の力をふっと抜かせ、多角的で少しシニカルな視点に、独特の「粋」を感じた。
森先生の子どもの頃・・・。いったい、どんな少年時代だったのだろう。
* * * * * * * * * * *
『僕は今の時代を半世紀以上前に歩いていたような気がします。核家族の一人っ子で、ついでに言うと、親は高学歴で無財産という、割に今ならよくある家庭で育ちました。
僕の親父は山陰生まれで、子ども時代に両親を亡くして本家に預けられました。「この子は勉強でもさせにゃ、しゃあない」と育てられ、高等師範学校を卒業し、中学の教師をして金を貯め、京都大学で物理学を学びました。それから東京の外資系の会社に就職し、30年恐慌でリストラに合ってしまう。本当に「今風」なのです。僕は関西出身と思われることが多いのですが、当時、昭和3年に東京の大田区で生まれました。
関西に知り合いが多かった親父は一家を連れ、僕が5歳の頃、大阪に移り住んだのです。あちこちから資金集めをし、今でいうベンチャー企業の小さな工場を始めました。戦時中は調子がよかったのだけど、戦後になってから再起し損なってあとはガタガタ。財産は全くゼロです。その頃住んでいたのは、大阪の豊中市の借家でした。
豊中というのは阪急宝塚線の古い住宅地で、東京の田園調布よりも古い歴史があるのではないでしょうか。当時の大阪は、デパートというと心斎橋あたり、劇場は道頓堀で、その辺りは昔から賑わっていました。宝塚線は「サルかキツネを乗せるのか?」と言われるような何も無いところだったので、「いつでも座れる阪急電車」と言われていました。ところが、片一方の端に阪急デパート、もう一方の端に宝塚劇場、そしてその間に住宅地を作ったので、どんどん栄えていったのです。それが大正時代のことだから、当時にしてはなかなか新しい発想だったのでしょうね』
新しく立ち上げた工場で泊まり込みの日々が多いお父さんだったから、始終くっついているような父子関係ではなかったが、可愛がってもらった記憶が森先生には残っている。お母さんもやはり自分の世界を持っていて、ベタベタするような母子関係ではなかった。そしてそれは森先生にとって、なんとも居心地のいい家族関係だったのだ。
『お袋は若い頃から大の宝塚ファンだったのですが、僕が生まれてからは僕を育てることをとても楽しんだらしいのです。けれども僕が小学校2、3年になると、また宝塚熱がぶり返した。宝塚劇場に一緒に連れていってもらいましたけれど、僕なんてそっちのけでした。
我が家は宝塚線沿線だったこともあり、近所に宝塚の女優さんがたくさん住んでいたので、なぜか宝塚の女優さんのたまり場になっていました。宝塚のお姉さんたちに、僕は随分可愛がってもらいました。トランプや麻雀を教えてもらったり、「風と共に去りぬ」とか「誰がために鐘は鳴る」とか、お姉さんたちが読んでいる本を真似して読んだりしました。当時、我が家には様々なジャンルの本が雑然とあったのです。お袋は昔の文学少女がそのまま大人になったような人でしたから、あらゆる作家の本を読んでいました。その影響で、僕も家の本棚から引っぱり出してきて何でも読んでいました。内容がわかるから読むというより、本の中での外国旅行という気分でした。中でも戯曲が特に好きだったのです。「シェイクスピア」などの脚本もたくさん読みました。
お袋は脳天気な性格で、戦後、家が傾いたときにも、牛肉を食べたいと思ったら、いちばんいい牛肉をツケで買ってくるのです。そのツケがどんどん溜まるでしょ。溜まると昔からの馴染みの店が2、3軒あったので、順番に違う店で買う。金が入ると、一番古いツケを払って、またそこで買ってくるというような、まるで飲み屋通いのスタイルなんです。酒は全く飲まなかったからよかったけれど、時代が時代なら、カードローンで身を滅ぼしていたかもしれませんね。本当に好き勝手に生きている人でした。
それから、もうひとつ面白かったことがあります。僕は身体が弱くて、僕よりも元気のない子を他に見たことがなかった。日本一、元気のない子だと自分のことを思っていました。身体検査では、優・良・可のうち、いつでも可だったのです。体操なんて、まるでダメ。それでも、昆虫少年だったから、虫採りをするのは好きだったのです。当時、阪急電車主催の昆虫採集の会があって、「ちょっとは外に出た方が、この子も元気になるだろう」とお袋が僕を連れて参加しました。でも、結局、現地に到着してみたら、お袋のほうが昆虫採集に熱中していました。僕はただただ、ぼうっと座って、元気よく蝶々を追いかけ回すお袋を遠くから見ていました。とにかく自由で気ままな人だったのです』
気ままなお母さんと、宝塚の女優さんに囲まれて育った森先生は、一人っ子でありながら巧みな社交術を知らず知らずのうちに身につけていた。
『一人っ子は協調性がないと言われるでしょう?でも僕は、いじめられたことがなかったのです。考えてみれば、「あ、森か。森はしゃあないな。あれは仲間と違うもんな」。そんな風に気持ちよく、仲間はずれにしてもらえた。一人っ子は、割に孤独に強いのかもしれません。中学くらいのときは、家に帰るとお袋は宝塚に行っていて留守ということが多かったので、一人でいることは全く平気でした。反面、たまに人に会うと、「おっ、森か!」と珍しがられて歓迎されて楽しい時間を過ごすのだけど、あまり長くはひとつのところに居着かなかったのです。
社交性というのは、いわば人との距離の取り方ですよね。その点を僕はいつも気にかけていました。お袋には勉強のことで意見されたことはなかったけれど、社交的にまずいことは注意されたのです。
例えば、宝塚のお姉さんがグラビア雑誌を見ながら、「(掲載されている女優さんの)目が素敵ね」と言ったとする。そこで、同調するのはよくない。あざといのはもっとよくないけれど、「目はその人のほうがいいけど、口は貴女のほうがいいです」なんていう風に返事をする。つまり、女性が自分以外の同性を誉めたときには、それに同調しないで、その人のいいところを誉めろって。だからと言って、あまり誉めすぎもよくない。それを教わったのは、小学生の時です。年をとってからは役に立っているような気がしますけど、当時の子どもとしては、僕はませていたでしょうね。
これは、職場の同僚や友達にも言えることです。「Bは、あそこがいいところだな」ってAさんがBさんを誉めたときに、返しワザとして使える。Aさんがそんなことを言わないうちから、「Aさんは、ここがいいところ」とこちらからわざわざ言うのはおかしいけれど、「Aさんの長所はここ!」というのを心の中にいつでも隠し持っているのが社交術の極意なのです。つまり、相手についての誉めどころをいつでも心の中に持っていることは大切かもしれません』
軍国教育盛んな頃、中学生になって、大阪府の北野中学に通う。体力的には、か弱い少年だった森先生は軍事教練が大の苦手で、手榴弾を投げても、俵上げをしても、なんとなくパッとしなかった。
『軍事教練が嫌だったからというわけでもないのですが、僕は中学2年頃になってから、学校をさぼることを覚えたのです。親父から、さぼるのだったらこの二つのことを忘れないようにと言われました。「むやみに休むと落第してしまう。みんなが学校に行っているときに休むのは自分の責任なのだから、自分でスケジュールを組みなさい。スケジュール管理ができないなら、さぼる権利はない」。あともうひとつは、「休むなら休むなりに、学校に行くよりも、いい一日を送るように」と言われました。中学生の僕にとっては、親父のこの言葉は、とてもプレッシャーでした。後になって思えば「自由に伴う責任」ということを、親父は言っていたのでしょうね。
さぼることを覚えたり、先生の言うことを聞かなかったり、模範にならない生徒でしたね。時々は先生に詰め寄ったりもしました。僕が詰め寄った先生は、校長先生には従うのに、生徒に向かっていばりたがるという気の弱い先生、つまり、生徒からは人気がない先生だったのです。詰め寄るのは、あまり公にやらず、しかも第三者がいるところでやる。ちょっと問答になって、ちょっと挑発して、そして適当なところで、「まさか、先生。中学生との議論に負けて、手を出すのとちゃいますよね?」って。その後は、「なんなら、他の先生も交えて議論しませんか?」と言うのです。
これも「社交術」と関係するのですが、京大に来てから、ボスの教授には気を遣うのに、教授がいないところでは急に変貌してしまう人を見たのです。僕はあまり気を遣わなかったけれど、年輩の方は大切にしたほうがいいからという単純な理由で、大切にしていました。でも、年輩の方もこっちのそんな気持ちを知りながら、その距離感を楽しんでいるのだと思います。もし、愛嬌だけでべたつかれたら気持ちが悪いし、若者というのは、いくらか生意気なのは仕方がないと思うのです。だけど、生意気一途というのも始末に悪い。要はバランスの問題で、「愛嬌には生意気のスパイス、生意気には愛嬌の隠し味」を持っていたほうがいいのです。ところが、このごろはなぜかそういうことを単純化したがる傾向が強いようです。先生は尊敬しなければいけないとか、年取った人を敬えとか、言い過ぎるような気もします。僕自身は、若い人からそんなことをされたらいい気持ちがしません。なぜか、人によって、愛嬌が表に出る人と、生意気が表に出る人といるけど、これが単純にどちらかだけになってしまうのはとてもつまらない。その点では、僕は処世術が上手かったのかもしれません。
学生時代は戦時中だから、正しいことを人に広めようと思うと弾圧されてしまう時代です。そこでわかったのは、正しさは伝わりにくいけど、楽しさは伝染しやすいということです。「こんなんおもろいで、こっちのほうがええで」というのは割合伝わっていきます。正しいから広めようというのではなくて、楽しいから伝染してほしいと思っていると自然に周りがそうなっていく。でも、他人が楽しんでるのをひがむ人もいるから、その辺をうまくやるのはなかなか難しいのです』
昭和22年、三高から東大に進む。京大ではなく東大に進んだ理由は、当時の東京に身を置いて戦後体験をしてみたかったから。それでも、憧れの東京は、想像していた以上の焼け野原で、お茶の水から本郷の赤門のところまで何ひとつ残っていなかった。
『そんな時代でも、僕は結構、楽しくやっていました。東大の数学教室に、用務員のおばあさんがいる部屋があったのですが、先輩や卒業した人たちがしょっちゅう集まっていました。いつもなにやら面白そうな話をしていたのです。僕は入学したばかりなのに、そこに出入りしていました。授業はあまり聞かなかったのですが、そこに行っては先輩たちの話に耳を傾けていました。
「数学」の世界は、割に気楽なものでした。なぜ数学に進んだかというと、小さい頃から数学少年ではあったことは確かなのだけど、数学なら兵隊にならずにすむということも大きな理由です。旧制高校で理科や物理で大きな顔をしているよりも、文学や思想を論じている方が圧倒的に格好よく見えたものですが、リルケがどうのこうのなんて言ってると、兵隊にとられてしまいますからね。僕らの時代は、理系・文系でいうと、文科が1クラスで、理科は8クラス。戦争には技術者が必要だから、大学で理系に進む人は圧倒的に多かったのです。物を作る人は工学部、勉強は好きだけど物づくりは面倒という人は理学部、野原をウロウロしたい人は農学部、人付き合いが好きだと医学部、と、こういう感じでした。面白いのは、なぜか文系サークルには医学部の学生が多かったことです。当時の町医者は、つきあいも広くて博学で、芸術にも素養のある人が多かったのです。明治・大正の文学者は医者や理系の人が多かったのです。
数学についていえば、世間の数学に対しての見方はなんだかおかしいのです。決まった問題を、決まった方法で、決まった解答を出すという風に考える人がとても多い。でも、定石どおりに誰にでも分かる方法で解いたところで、誰も認めてくれる世界ではないのです。従来の概念とは違う方法で解いてはじめて、「あのやり方は何か役立ちそうだ」と認めてもらえる。ところが世間から見た数学のイメージは、とても堅いものです。
「あいつの発想は他のヤツとは違う」ということが、数学の世界では珍重される。そういうところに身を置いたことが、僕には合っていたと思います』
関西と関東での大きな違いは「あいつ、けったいなやっちゃ」というのが誉め言葉で、変わっていることを面白がるという伝統が関西にはあるそうだ。子どもの頃にはそういう文化がもっと色濃く出ていた。
『「20世紀は凡人の世紀、21世紀は変人の世紀」なんて言うけれど、皆が同じということが、20世紀まではプラスの価値でした。ひとつの標準があって、皆それに従うことを良しとされ、だから、「協調性」ということが重んじられたのでしょう。けれども21世紀は、都市化・流動化して、少子化・核家族化もどんどん進んでいく。「人と違う」時代になっていくのは否めないのです。でも、ただ漠然と他人と違うだけではいけないから、なおさら、社交性が大事になってくると思います。現在の家庭環境では、家族の絆が大事だとか、地域との絆が大事だとか、20世紀のイデオロギーが残りすぎているように思うのです。これからは、絆を作って安定していくというのは難しいのかもしれません。日本に持ち家が増えたのは農村から来ていて、今でも田舎のほうでは大きな家を建てるお城文化です。ところが、都市というのは流動的なので、生まれた家で死ねる人はあまりいない。家は「移っていく」のが、だんだん当たり前になっている。
パスカルの論理を関西弁に翻訳すると、「神さんちゅうもんは、おるかどうかわからん。そやけど、おらんと思うて好き勝手して、死んで神さん出てきたら、えらいことになるで。神さんおるはずだと身を慎んでいて、神さんおらんということになっても、そりゃ大したことはない。そやから、絶対に、神さんがおるほうに賭けた方が得やで」。これはつまり、「世の中が流動化するのか、安定化するのかわからないけれど、今のところの流れとしては流動化するだろう。安定を求めて苦労するよりも、流動化しても大丈夫なようにしておいたほうが得ですよ」ということになるのでしょう。
協調性を口にするのは20世紀までで、これからは社交性でいかなければならないのではないでしょうか。「協調性」と「社交性」は、方向が真反対になるのです。協調性はひとつの文化共同体があって、それに溶け込むというか、一致すること。社交性というのは、異文化と付き合うことを面白いと考えること。自分と年が違ったり、ジャンルが違ったりする人と付き合っていく。そういう人と付き合ってみることで、世界が広がっていく。今の時代は、明らかに抑圧されすぎているのです』
地域や家庭の絆を日本人は意識し過ぎて、地域現象・家庭現象ということが、人に対して抑圧的になっていると森先生は言う。「愛情」についても、ひと呼吸おいて考えてみると自ずと見えてくることがある。
『少人数教育が大事だと言われて、「子ども一人一人に目が届くように」とか「一人一人に愛情を注ぐ」と教育現場で言うことが多いけれど、それはもしかしたら、子どもからすればとても窮屈なことかもしれません。「大人の奢り」なのではないでしょうか。
人間関係でも、少人数というのは厄介なものです。子どもたちが先生に文句を言うことで多いのは、「えこひいき」の問題です。少人数だと自然とそうなってしまうのです。個人対個人になってしまって、相性がいいか悪いかという問題になってしまう。例えば、大学のゼミでも、5人のグループだとしたら、3人対2人とかに分かれてしまったりする。それが40人もいる教室なら、いろいろな人間がいるので、もっと自由にバラバラになることができる。少人数で形成されたグループで、他のメンバーに文句を言われないようにしようとか、皆が平等であるべきだなんて言い出すと、考え方はどんどん官僚化して狭くなってしまうのです。
感情と、人間はそれぞれが違う、ということをうまくコントロールしようとすることは、非常にデリケートなことです。これはある意味の社交性で、生きていく上でとても重要なことだと思います。そのことが大切だということを現在の人たちは忘れていて、皆が平等にとか、子どもには愛情を注いだほうがいいとかを言い過ぎるような気がするのです。
「教師の思い通りにはならない生徒が現れるから面白い」という考えが京大では強いのですが、これは親子関係でも言えることではないでしょうか。親の思った通りに子どもが育ったら、それは果たして、子育てに成功したことになるのかどうかよくわかりません。
僕もよく「思った通りにお子さんは育ちましたか?」と質問されましたが、「子育てというのは、原則的に失敗するもんやで」と答えていました。親というのは子どもに対して誰しも「こうなってほしい」という思いがあるものだけど、そうならないから親子なんじゃないかなあとも思うのです。
手をかけ過ぎても、かけなくてもいけない。程よい加減というのがあるでしょう。学校でも家庭でも、身体的にではなく、教育的に子どもに手をかけ過ぎているのではないでしょうか。これからの時代は、もう少し、親子ともに自由になることを覚えなければいけないのではないでしょうか』
* * * * * * * *
『昔の子はよく勉強したというのは本当だけど、何かに役立つから本を読んでいたのとは違うのじゃないかなあ。男の子は大体、20歳までに死ぬと言われていた時代だから、今読んでおかないと後で読むことはできない。後で役に立つからと考えているのではなかったのです。
僕が大学を卒業したのは1950年だけど、その頃は図書館に行っても、外国の本を含めてもあまり本のなかった時代です。テキストもないから授業を聞くしかない。それから10年くらいして、京大で教えるようになってからはテキストが当たり前のようにあった。最初の頃は、テキストの通りにやっても生徒は面白がってくれないから、ちょっと横道に逸れたことを講義していました。でも、今から30年くらい前から、「なんでテキストと違うことをやるのですか?」と学生は変わってきた。その頃から、標準のコースに沿って進もうとする人たちが増えてきたのです。
みんながみんな、決まったコースになぜ進まなければいけないのでしょうか。何かの目標を決めて計画を立ててそれに沿って達成するという20世紀スタイルが強すぎたのかもしれません。でも、途中で転向してもいいと思うのです。大学だって、入学してから途中で転向してもいいと思う。むしろ、途中で転向した人のほうが人間としては面白味があったりします。
青春の時代は、新しい時代を感じ、新しい自分を探っていける。それを、決めつけてしまうことはないと思うのです。いつの時代も、その時から10年すると物事は変わっていく。だから、10年先のことをあまり決めても仕方がないのです。決めれば安心するというのは幻想でしかないですからね。
「決まってないから、いろいろあっておもろいで」。そう考えたほうが、人生は何倍も豊かになるのではないでしょうか』 (インタビュアー 三上敦子)02.10.1
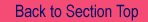
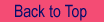
Edited by Atsuko Mikami