


2003年1月、朝日新聞社主催による朝日社会福祉賞に2氏1団体が選出された。聖路加国際病院理事長の日野原重明先生、「女性の家HELP」、そして「難病のこども支援全国ネットワーク」専務理事の小林信秋さん。日野原先生は新しい老人福祉文化の形成にご尽力されていること、「女性の家HELP」は暴力を受けた女性・子供を受け入れるシェルター活動を16年間されていること、小林さんは難病の子供・家族に目を向け、新しい福祉の対象分野を確立されたことを評価され受賞された。
今日は、「難病のこども支援全国ネットワーク」の小林信秋さんにお会いしてお話を伺ってみた。小林さんは、毎年、東大小児科の子どもたちへのクリスマスプレゼントにと、サンタクロースを連れて病床を訪ねてくださっていた。小林さんの、病気の子どもたちに目を向けた活動はどうして始められたのだろう。
治療法もなかなか確立されない小児の難病は500種類以上、患者さんは全国に20万人以上もいるといわれる。しかし、お年寄りや障害者と比べるとあまりにも少なく、福祉の分野で理解され援助されることがあまりなかったのが現状だ。小林さんは約20年間に渡り、その患者さんや家族の方々の橋渡しとなり、難病の子どもたちの生活の質を向上させるべく活動されてきた。活動のきっかけは、1980年、小林さんの長男の大輔君が「亜急性硬化性全脳炎」(SSPE)という麻疹のウイルスが脳を壊してしまう病気になり、2〜3年持つかどうか・・と診断を下されたことからだった。
* * * * * * * * *
『息子を在宅で見ているころ、主治医だった二瓶健次先生から「親の会を作ってみませんか?」と声をかけられたのです。女房は、すぐに他のお母さん方と動き始めました。そういう時、男親というのは、「そんなことでお互いの傷をなめ合っても仕方がないじゃないか」という考え方をしてしまう。僕はすかさず、「子どもの面倒を見なければいけないのに、誰がそんな活動をやるんだ?」と聞いたら、女房は間髪入れず「貴方がやるのよ」とあっさりと言うのです。
女房の一言で僕も真面目に「会」のことを考え始め、(こうしようか、ああしようか・・・)とあれこれ考えあぐねながら、同じ病気の子どもたちや親御さんたちと交流していきました。そうしているうちに集まりが10家族になり、「青空の会」という名前をつけ活動を本格的に始めることになったのです。
闘病のことで悩んでいる親御さんから相談がきたりするだろうと想像はしていましたが、電話でのやりとりは電話代がかさんで大変です。そこで「文通をしてみてはどうだろう」という発想から、機関紙を発行することになったのです。一度発行すると、読んで下さったご家族から手紙が来て、手紙を次の号に掲載すると今度はその手紙に対しての便りが来る。記事はどんどん増えていきました。当時は手書きで作成していましたので、出張先に原稿を持っていき、仕事が終わってからビジネスホテルの部屋で作業したものです。毎月必ず発行していたので反響がどんどん大きくなり、親御さんたちからたくさんの電話がかかってくるようになっていました。そのときに「あなたはどういう人ですか?」と質問をされるので、「あなたのお子さんと同じ病気を持つ子どもの親です」と答えると、もっと頻繁に電話がかかってくるようになったのです。子どもを個々で介護していると、外からの情報は皆無に等しい。どうしようもなく孤独になっていきます。だから親御さんたちは藁をも掴む気持ちで、生の情報を入手したいと思うのでしょうね』
親御さんたちの輪がそうして広がっていくと、明るい日差しが少しずつ差してくる。悩み相談ばかりだった電話もいつしか楽しい計画を相談する電話にもなっていった。
『「みんなでキャンプに行きたいね!」という話が出るようになって、夏に、伊豆の湯ヶ島に2泊3日で出かけることになりました。どの家族も子ども達を連れて遠出したことなどなかったのですが、遠方からもたくさんの家族が集まってきたのです。子供が20人くらい、親御さんや家族も含め総勢60〜70人くらいにもなりました』
小林さんはキャンプなどの行事を開催する傍ら、医薬品の保険認可や難病指定の運動も着実に進めていかれた。
『SSPEには適切な薬がなかったのですが、息子はある薬を飲み始めてから、みるみる効き目が表れてきました。ところが、その薬を使用する患者数が少ないため、製造しても採算が合わないから製造中止にするということになってしまったのです。効果がある薬なのに採算が合わないから輸入を停止されるということに強く憤りを感じました。当時の僕は厚生省が何処にあるのかも分からなかったのですが、調べて、厚生省まで話をしにいきました。運良く、オーファンドラッグの制度を日本に取り入れた方に会うことができました。その方がとても熱心に対応してくださったおかげで、臨床試験の後、息子の使用していた薬はオーファンドラッグとして使えることになり、その2年後には保険薬として認可されるようになったのです。
その後、「どうしてこんなに大変な病気が難病指定ではないのだろう」という話があちこちの家族から聞かれるようになりました。その意見を持って、今度は役所に行きました。けれども役所では全く取り合ってもらえなかったのです。それならばと、国会請願の署名活動を始めました。会員60家族が一丸となって18万人の署名を集め、2回目の国会で採択されたのです。それから新聞、雑誌やテレビで大キャンペーンをしました。正規の署名用紙には18万人だったのですが、それ以外に便箋などに署名をしていただいたものが数10万人にもなりました。
その頃の僕はコンピューター会社に勤めていました。マイコンの応用機器開発や、何千万円もする大型コンピューターの営業をしていたのです。当初は記憶装置が紙テープの物だったのですから、現在とは全く様子が違うと思います。
仕事は一所懸命やっていましたが、僕はサラリーマンが好きではなかった。だからというわけではないけれど、息子の介護のほうに夢中でした』
そんなとき、1988年。お世話になっていた小林登先生の紹介で、SSPEに限らず「難病のこどもを支援する活動」に専念することになった。
『まず、「電話相談室」を始めることになりました。相談をしているとさまざまな電話がかかってきて、病院のこと教育のことなど、多くの人からの話を聞いているうちに、(もっともっと、みんなで話し合える場所が必要なのでは・・・)と感じようになりました。そこで、シンポジウムを開くことにしたのです。シンポジウムを開いてわかったことは、子どもを支えるのも親を支えるのも、親の会というのがとても重要だということでした。それから「親の会連絡会」を作りました。親の会連絡会を始めてから難病の子どもの教育がほとんどされていないこともわかったので、「病弱教育セミナー」というのを立ち上げました。こんな風にひとつのことを始めると、知らず知らずのうちに枝葉が広がっていったのです。相談室を開いたらあれもこれも必要なことがわかり、「それなら次はこれをやってみよう」というように、どんどん必要なことが増えていきました。
夏のキャンプは「友だちをつくろう」をテーマで、毎年4箇所で開くようになりました。神奈川、愛知、大分、宮城の4県のそれぞれに実行委員会を設置していて、例えば宮城県を例に挙げると県立こども病院がもうすぐできるのですが、そこで働いているスタッフが窓口になっています。九州では、ボランティアの方々。神奈川では家族の会。キャンプに参加可能なのは先着150名なので、蔵王でのキャンプは告知するとすぐにいっぱいになり、難病の子どもがいる家族だけで出かけるという機会は非常に少ないでしょうし、また、このキャンプでは同じ病気の子どもたちが全国から集まってくるので親御さんが他のメンバーに気を遣う必要が全くない。その辺りがとても居心地がいいのでしょうね。魚のつかみどりをしたり、カヌーに乗ったり、たくさんのイベントをして、「とにかく楽しければいい!」というキャンプなのです。
サラリーマンを辞めて生活のために小さな所に就職して、安月給でしたが収入は得られるようになりました。女房は老人保健施設でお年寄りの世話を始めました。それから10年活動していたのですが、1998年に「難病のこども支援全国ネットワーク」という現在の名称で活動母体を設立することになったのです。
なぜか活動を続けていくことに不安はありませんでした。とにかく、無性に、「この活動をずっとやっていきたい」という気持ちのほうが先に立っていました。それと僕は大雑把な性格なので続けてこられたのかもしれません。自分のことをかなり鈍感な性格だと思うし、深く追求して物事を考えない。だからできたのかもしれません。「これは面白そうだな!」きっといつも楽しいことを考えてきたから、続けられたのだと思います』
事務所の中では、てきぱきと明るく電話相談をされている女性の姿が見られる。大輔君が当時とてもお世話になった看護師さんが、電話相談の窓口をされているのだ。そして、小林さんが力を入れているひとつに、「プレイリーダー」の養成がある。
『入院している子どもたちの傍にいて一緒に遊ぶボランティアなのですが、この頃はあちこちの病院からの要請が増えています。実習を受け入れてくれる病院もだんだんと増えてきました。何事もそうですが、始めるときはどうなるかわからないけれど、やっていくうちに開けていくことも多いのですよね。ただ、全国で小児病棟が減ってきているので、実習先の機関もそう多くはないのが現状です。けれども、ボランティアでやってみたい、プレイリーダーとして活動してみたいという方は年々増えています。その多くはやはり、患者さんの親御さんです。ご自分の経験を生かせたらと考える方は多いのでしょうね。
それから、難病の子どもたちの「教育」という点にも力を入れています。国に小児慢性疾患の子供に医療費を補助する制度があるのですが、「難病のこどもの教育を考える」というシンポジウムのときに、ある審議会があり、「慢性疾患の子ども達について対策を練ろう」ということも医療費補助の他に追加事項としてもらえたのです。それがきっかけとなって、「病弱教育セミナー」を始めました。その活動も10年くらい経ちますが、特殊教育の分野に於いて、だんだんと知名度が上がってきたのです。実は、何年か前から普通校へ行きたいという子どもが増えていますが、普通校の受け入れ体制は未整備です。一昨年、小児慢性疾患の検討会を厚生労働省が作って下さったのですが、そのときに提案させてもらいました。そしてやっと今年の秋から、「養護教育セミナー」を開けることも実現したのです。
仲間達は僕のことを、ぽっと考えたことを思いつきでやるように思っているらしくて、「打ち上げ花火」が好きなように思っているようです。でも、「養護教育セミナー」にしても何年も前からずっと頭の中で考えていて、「いつかはやってみたい」と強く思っていたことです。プレイリーダーも何年も構想を練ってようやく始めたことなのです。でも、心の中で温めていたということは周囲には伝わりにくいものですからね。
それでも僕は本業以外には全く関心がないのです。福祉のことは、ひとつ始めるとさまざまな問題に手を広げる人も多いと思うのですが、僕は難病のこどもたちのことからあまり踏み出さずに、この中の活動を広げていきたいと思っています。それと、70点主義者なんです。完璧を求めない。100点を取ろうなんて全く思わないのです。適当に手を抜いて70点で終わらせれば、活動の中で足りない点にも気が回るようになりますから。でも、要するに怠け者なのかもしれませんね』
大らかで明るく闊達な雰囲気の小林さんは、東京渋谷区で生まれ育った。最寄り駅は原宿だったので、明治神宮や東郷神社が子どもの頃のいちばんの遊び場だったそうだ。23歳で結婚され、大輔君、お嬢さんがひとり、ふたりと、26歳の時には3人のお子さんのお父さんとなっていた。
『振り返れば、そのときが一番楽しい時代でした。息子が生まれてから病気になる数年間が、人生の中で最も楽しかったのかもしれません。僕は子どもと一緒にいることが本当に楽しくて、完璧なマイホームパパでした。休みになると3人の子供を連れ出していました。女房に弁当を作ってもらって近くまで遊びに行くのです。もちろん家族5人で行くこともあるし、毎週のように必ず家族で出かけていました。友達にはゴルフや麻雀をする人もいましたが、僕は全く関心がなくて、子どもと一緒にいることの方が嬉しかったのです。子育てが楽しかったのです。お風呂も、おむつ換えも、寝かせるのも、買い物も、僕は結構やったと思います』
* * * * * * *
『サラリーマンを辞めて電話相談室を立ち上げてすぐ、息子は13歳で亡くなりました。発病してから8年経っていました。あれからずっと、僕は死んだ子の年を数えながら生きています』
一緒にキャンプを楽しんだ「青空の会」の子どもたちの写真を微笑んで見ている小林さん。折り畳んだ想い出をふっと解くような柔らかな表情になっていた。小林さんの活動は、難病の子どもたちや親御さんを勇気づけるのはもちろん、誰もが、ただ元気でいられることの素晴らしさを考えさせてもらえるような、日常を省みるきっかけになるような気がしてならなかった。
ますます楽しい活動が広がっていかれることを心から願ってやまない。
(インタビュアー 三上敦子) 2003.4
・・・お知らせ・・・
「難病のこども支援全国ネットワーク」では、ただいま会員募集中です!
詳しくは下記までご連絡ください。
〒113-0033 東京都文京区本郷1-15-4 文京尚学ビル6F
TEL 03-5840-5972 FAX 03-5840-5974
URL http://www.nanbyonet.or.jp E-mail ganbare@nanbyonet.or.jp
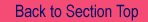
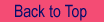
Edited by Atsuko Mikami