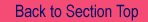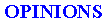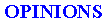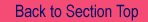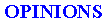
第111回哲学研 結婚について 2002.2.19
Aさんの気持ちの中で、そろそろ結婚しようかなと思ったのはどうしてか?
自分はMさんが葉書を送ってくれなければ、結婚する気はなかった。自分は積極的に結婚しようとも思っていなかったし、半分諦めていた。結婚して、食事、掃除と女性に家政婦の代わりを求めるのは失礼。
それでも結婚に対してはどう考えていたのか?やってみたいと思っていたのか?
子供は欲しいと思っていたが、だからといって、積極的にどうこうしようとは思ってはいなかった。
確かに、子供のことは、結婚のかなり大きな要素かも知れない。
子供を持って、どうしたいと思ったのか?
おこがましい意味ではないが、育ててみたいと思った。娘を見てて、日々勉強。あの子を見ていると、血がつながっているいないに関わらず、子供は別人格だというのがよく分かる。
それは、病棟の子供達とどう違うのか?
病棟の子供達だって別人格だと思うが、近い分だけその思いは大きくなる。
自分も昔は子供が生まれてそう思った。血のつながった子供が生まれるのはどんな感じだろうと思っていたが、生まれた瞬間、自分とは全く別に生きているんだと。
それは、男性だからそう思うのではないか?女性は自分が生むから、そういう風には割り切れない所があるのではないか。
確かに、母親にとっては身体の一部だと思っているかも知れない。
自分の奥さんは息子が生まれた時に、「おなかの中からこんなものが出てくるのか」と言っていたぐらいだから、生んだ本人は自分の身体の一部だという意識がかなり強いのではないか。
家の奥さんはあまりそう思っていないみたい。子供が大きくなったら、二人で好き勝手に暮らすのがいいかなと言っているから。
うちはそんな話はしたことがない。少なくても、そういう保障はない。
Aさんのところは、娘という共通の的があるから、夫婦が結びつくところがあるのか?
自分も奥さんも、子供中心と言えばそうだが、彼女も子供べったりではない。
うちは子供の話しがないと話題がないかも知れない。他に、何か夫婦で話をしているかと言えば少ない。
端から見てて、Iさんのところは、良い意味で、お互い良い距離を持っている。ちゃんと気を使っているというか。それが、Iさんのところの夫婦の形なんだろうなと
思う。
反アメリカという点では話が一致した。天皇制に関しては、微妙な食い違いがあるが、政治的な話とか、宗教、民俗、そういう話もするようになってきた。
付き合っている時は、そういう話はしなかったのか?
しなかった。
うちは、文章でも書こうかなと言ったら、やったらと言われて、それ以上話が続かない。付き合ったら話が止まらなくなるのが分かっているからだろうが。
恋愛と結婚は全く違う。恋愛感情は結婚すると全く起こらない。恋愛感情があって結婚したから、家族になるわけだが、日常が始まってしまうと、以外と速く恋愛感情が消えていくのではないか。むしろさっき言ったように、何の話を二人がするのかに力点が移るのだろう。Iさんは、奥さんと政治問題を初めて話すようになったが、一般的にはそんな話はしない。うちはそういう話を絶対しないのは、自分が一方的に喋るし、それにねじ伏せようとするから。
結婚前の恋人関係の時には、むしろそういう話を積極的にするのではないか。
自分は、そういう話をするだけのものが自分の中に何もなかったからしなかった。
恋愛と結婚では、話題が最も変わるのではないか。だから政治的な話題は一切避けられる。それまでは、それなりに自分の考えを述べ、相手も反応する。結婚してからはまず無い。子供ができれば、相当無くなる。
結婚するまでの過程で、話をしなければならないことがたくさん出てくる。
そういう意味では、自分みたいに母親が死んだりすると、具体的な小さい話題が共通に出てきている。それは今までで初めてのことである。自分が働いている時には、自分の世界があって、相手に話しても「ふん」なんて言われるだけで、相手は相手で、近所のおばさんの話をするから、全く交流の場がない。せいぜい子供についての意見を話すぐらいだった。それが全部終わってしまって、自分が具体的な事実に眼を向けはじめると、相手もそういうものに眼を向け始めるが、そういう関係が良好なのかも知れない。しかし、それは子供が大きくなってからである。子供が小学校くらいだと子供の話がほとんど中心になる。だから、恋愛をしている時の延長で、話しを続けることはないのではないかという気もする。何となく避けておいた方が安全という気もする。1つの考えがはっきりと相手に見え出してくるということは、結婚してなければそれが美しくも見えたりするかも知れないが。
子供がいない場合は、その方が良いのではないか?子供がいた場合は、確かにきついかも知れないが。しかし、この前Nさんの家に行って思ったが、父親と母親はずっと若い頃から、お互いに志をちゃんと話してきたのではないかと、すごく思った。
母親も仕事に対してとか、自分が音楽をやってきたから、そこは譲らないで保ち続けて、二人が同じような方向にきたのではないか。
良い意味で、ちゃんと子供を巻き込んでいるというか、家族が一体化している感じがする。「出動!」とか言えば、一緒に出動しそうな感じがする。
家の父親もそういう父親だった。だから、もちろん世の中の考え方も、自分の考え方も喋る。家族はそれに全面屈服だから、母親がそれに意見を言うことはない。溺れかかったら、父親の元に馳せ参じる仕組みにはなっていた。だから、今はそれがだんだん消えてきているのかも知れない。
Nさんの家が古い感じがしないのは、母親に新しい結婚の眼があるからである。だから、母親の考え方によって、相当夫婦の中身が変わる。恋愛する時に、恋愛感というものが対等で、お互い仕事を持っているような相手を選んで、その仕事を遂行させようとするかどうかで、全然違ってくる。だから、相手が仕事を持って自分の考えを持ってやっている時に、恋愛は続くと思う。
結婚した人も、結婚する前どう思っていたかを聴きたいが、結婚したら、奥さんが家に居たほうが良いと思うか、働いたほうが良いと思うか?
自分は、結婚前は家に居てくれたら良いと思っていた。
自分はどちらでもいい。相手による。優先すべきものは他にあって、相手が家に居るか仕事を持っているかは、そんなに優先すべきことではない。
自分は、働いている人の方が輝いて見えていい。現実の生活で共稼ぎで子育てをしてという問題に絶対ぶつかると思うが、自分が仕事を続けたいという意志が強ければ、相手に折れて協力して欲しいと思うのではないかと思う。しかし、そういう場に遭遇してないので、イメージがあまりわかない。
自分も相手によりけりだと思うが、前妻は貿易関係の仕事をしていたが、恋愛していた時期に、貿易というのは毎年のように法律とかも変わっていき、新しいことをたくさん覚えなくてはいけなく、毎日が勉強みたいなことを聴いた。自分は向上心を持つタイプが好きだから、働きたいと思えば働けば良いと思うが、ただ強制はする気はない。
自分は、二人のうちはどちらかというと働いていて欲しかった。金銭的な問題ではなく、ある程度外に行って刺激を持って欲しいのと、自分だけを待つ人生をして欲しくなかった。母親みたいになってもらっては困るというのがあったが、子供ができてからは、どちらかと言えば家に居て欲しいと思った。もう一つは、出来れば家の管制塔になって欲しいと思った。母親が今まではそういう役割だったが、母親も好きなことをやり自分も働いていて、家族の重心が嫁さんになっているのが分かる。子供と一緒にいろいろやっているのが、それはそれで好きみたいではある。その中で友だちもどんどんできている。子供が小学校にあがって、手がかからなくなったら、何をしだすか分からないが。
自分の場合は核家族で、日本の長男=父親の家という雰囲気ではなく、妻=母親が家の中で気を使いながら暮らすというイメージは持っていなかった。ただ、もう一つの面があって、母親は専業主婦で常に家に居たのでそういうイメージもある。それを見本にしていたわけではないが、結婚したら役割を押し付けようというのはないほうで、何となく家に居て欲しいという感じがあったような気がする。自分には、ずっと付き合ってきた彼女がいて、8年付き合ったが、恋愛しているという感じも全然無く結婚した。結婚に対する具体的なイメージが結婚前からわりとできていた。現実に結婚してみると、彼女が家に居る状態がしばらくあって、こういうものだと思っていた。
うちは奥さんがテニスの審判をやっている。いつも顔を突き合わせるのは嫌だし、彼女もそう思っていると思う。魚を見ている時は一緒に見ている。趣味の部分は一致して、彼女はテニスをして自分は仕事をする感じになっているのが、好ましいとは思う。ずっと家に居るとなったら、年ととればとる程重荷になるという気がする。
個人的には、結婚に憧れていた20代前半までは、家に居てもらいたいと思ったが、今回結婚するにあたって、仕事をどうするかと聞いたら、彼女はいままで娘に淋しい思いをさせたから出来ればやめたいと。彼女の親もそれを望んでいて、趣味のマンドリンと着付けは続けたいのと、以前近所の子供や奥さんを集めてカルチャーセンターみたいなことをやっていて、それをやりたいと言うので、それは協力すると。
だから、やっぱり昔の母親のように、専業主婦という感覚は無いのではないか?趣味にしても何にしても、きっと価値がすごく増えているから、そんなに夫婦がべったりいるとか、だんなさんを待つというのは、かえってうっとうしいと思っているのではないか。必ずしも、働いていなくても、趣味とかで充分に自分の活動や生き方が果たせているから、ある程度距離が持てるのかも知れない。世の中が自然とそうなって来ているのではないか?だから、結婚の基本形態が変わりはじめているのではないか。先程の育児のことも、パリなんかでは男性が育児の本を読んでいる。もしかしたら、面白いかも知れないから育児をやってみたいと男性は思っているはずである。それは、一つの新しい傾向ではないか?
自分はあまり家で待たれるのは嫌だ。
今の人は放っといてもそうなるのではないか。子供が出来て仕事をやめても、勉強をしたいと思うだけでも距離を保っていられるのではないか。ただ、一番鬱屈としてくるのは、本当の専業主婦をやってしまうと、周りとの接触もなく、自分から外に出ることもなく、家で待っているとなると、奥さんは狂ってしまう。昔みたいに家事がものすごい量があるとなれば別だが、殆ど家事がなくて待っているとなったら狂ってしまう。
それに、昔の家事はそれなりに科学的で楽しかったかも知れない。漬け物を漬けてどう変わるかとか。確かに、洗濯にしても洗濯機で洗うのとは訳が違うから、綺麗にしてあげられるという喜びは大きいかも知れない。料理もそうだろうし。絶対自分の料理は美味しいんだと思って作っていたのだろうし。そういう意味では育児だけではなく、料理も男の人が作りたいと思うのは、家事をやる作業が楽しいと思い始めてきたからではないか。
料理はまだ自分の裁量が関係してくるが、洗濯はボタン一つで終わってしまう。楽しみもへったくれもなく、ただ面倒臭い。技術がいるのは干す時だけである。だから、昔は洗濯は大変だったけれども、何か楽しいと思える時もあったのだろう。川に洗濯をしに行って、知り合いがたくさんいてとか。家事が家事として好奇心を誘ったはずである。
洋服を作るのも楽しいはずである。保育園に入って、最初いろいろ作っていくが、楽しそうに一生懸命やっていた。楽しむ能力は女性の方が優れていると思う。
想像するにゾッとするのは、自分に子供が生まれて公園に行った時に、近所の母親達と人の悪口大会になった時、どうなるんだろうと思うと、きっと仲間に入れないだろうと思うが、そう思っている母親もいっぱいいて、そう思っている人はそう思っている人で集まるのだろうとは思う。友だちの話しを聞いても、類は友を呼ぶから、自分の友だちはみんなそれが嫌いで、子供が小さかった時、公園から回り道をして自宅と全く別の方向の公園で遊んでいたと言っていた。女の人は、一緒になって言わないと、のりが悪いとなってしまう。うちの母親はそういうのが面倒臭くて、だから似たのかも知れないが、近所のおばさん達の話しに入らなかった。働いていたのもあったが、いつか近所のすごく仲の良い人がいて、その人は何でも聞いたことを母親に教えてくれるが、「Mさんに話すとそこで止まって何でも話せるから良いんだけど、何か言ってものりが悪くって」と言われたと、自分に話してきたが、子供心にそういうことを聞いてすごく嫌だった。大人の女の世界は嫌だというか。だから、きっと主婦もそういうことでイライラすることもあるのではないかと思う。
うちの母親は専業主婦だったが、自分との間の距離はものすごく広くとっていた。全然見えないような格好で常にいるが、今から考えると、料理は美味しいが自分で作る料理はほんのわずかしかなく、コロッケを買ってきたりとかものすごく要領が良かった。ただ、それでういた時間は何をしているかというと、仏に手を合わせている。朝から番までずっとやっている。あの距離感はすごいというか、不良にもなりようがない。後ろから刀で刺すわけにもいかない。だから、あの距離の取り方は意外と斬新だったのかも知れない。ハルピンに居たからロシア料理とかが好きだったが、手垢にまみれた主婦にはならなかったみたいで、まして、世間話をやらない親だったから、そんな時間があるならいつも仏に手を合わせていた。その片方で、すごい合理的な、悪く言えば、いい加減なちゃらんぽらんな家事をしていた。美味しいと思ったら、自分では作らず、近くのスーパーから買ってきたものだけを食べさせていた。そう考えると、あの時代にすごくドライな考えをしていたあの距離感は、ある意味で、専業主婦のやり方としては優れていたのではないかと思う。
それは、祈るという自分の使命があるからだろう。何かを持っていないとそういう人になれない。
もし、そういうものがない人の専業主婦は、すごく子供に向かってしまうしかないのではないか。だから、これからは外へ向かう女性ということが、いろんな形となって出てきているのではないか。今の30歳ぐらいの母親は一番距離を取れない。塾でしか他人と接する機会がないから、競争になって子供に向かってしまうから一番悲惨。だんなからすれば、教育は女房に任せてあるからといえば済むが。
距離を保ちながらうまく育てる母親と、全く子供をほったらかして仕事とか遊びにうつつを抜かす母親は、見た目には似ているが本質的には何が違うのか。
それは、愛情ではないか。
それはどういう形で、子供に対してよい作用をするのか?
自分は、この母親は絶対自分のために命を捨てるだろうと小さい頃から思っていた。ただ、それは動作とかをずっと見ていると子供が分かることではないか?親は自分の身を捨ててでも自分を助けるだろうと。それを感じられないと、自分に向かってくる親に対して、子供が不安になってくる。それはあうんの呼吸のことだから、ものすごく詳細に記載しないと分からない。
同じ親に育てられても兄弟で全然違う。
不安定感が違うのはよく分かるが、何が違うのか?
やっぱり、何かあった時に、この親は自分を守ってくれるか、自分は捨てられるかで違う。
どこからそれが伝わるのか?
例えば、テレビを見て泣いたり怒ったりしている姿を見たり、寝ている時に布団を掛けるかそのままにされるかでも違う。あとは、怒られるにしても、真剣に怒っているか媚びて怒っているかは子供が一番分かる。自分の為に怒っているのか、感情で怒っているのか。
確かに、怒られるということははっきり気付くことかも知れない。褒める時は、逆に言えば、分かりにくい部分があるが、怒る時は子供が直に分かる事である。
母親によっては、「ちゃんと勉強しないと将来がないわよ」と怒る人がいるが、すごく微妙である。子供の為を思って怒っているような気がするが、母親の為に怒っている気もする。
それは子供には分かるのではないか。そういうことを言われたら、子供は母親は自分の事しか考えていないと思う。いくら母親は子供の事を考えていると言っても、その人間の質とか深さが出てくる。例えば、すごく貧しい家で、「お前が学問で身をたてる為に、自分は働いてもかまわないから、お前にはやって欲しい」という言い方をすれば、子供には分かると思う。しかし、「こういう大学を出て、こういう一流会社に入って」というところまで言われると、母親が自分の事を考えているとは思えない。
自分は怒られたことがない。一回父親に怒られたが、家出をしたので怒らなくなった。兄弟喧嘩しても、母親は絶対怒らなかった。
子育てで怒ってはいけないのか、ちゃんと怒ったほうが良いのか、堂々巡りになるが。
そのへんの書き方が今ものすごく重要だと思うが、怒る時に結果は分かっているがどういうふうに表現して良いか、という問題であるような気がする。それは、すごく哲学的な領域の事だと思う。つまり、自分の言葉はどこからでた由来のものか、自分の欲望から出た由来なのか、本当に相手方を想って出た由来なのか、あるいは、世の中全体の中で子供をこう見ているとか、というようなところまで分析はしないといけないのではないか。結局、自分の考え方、生き方が立派である時だけ子供には伝わる。そこでは、嘘を含んではいけない。怒っていても愛情が相手に分かる怒り方は、やっぱり嘘がないことである。それと、嘘がないことだけではなく、どれほど高いところを見据えて話しをしているかではないだろうか。昔の日本では教育が均衡であったが、それぞれの人たちは貧しいから高潔な心を持っていた。今それが行方知れずになっているのではないか。そうすると怒ってはいけないとか、ちゃんと叱りなさいとか書いてあるから、どうしたら良いのか分からなくなる。
それは、どちらでも良いような気がする。反面教師になって子供が「まったくなあ」と想うのも良いし、親が崇高な人でそのまま受け継ぐのも良いし、どちらでも良い気がする。あまり、怒ってはいけないとか褒めて育てるとかいうのは、自分は気持ち悪くて嘘臭い。頭にきたら怒れば良いと思う。
怒る前に自分で答えを作っているのもおかしいと思う。怒るという過程を通して、子供を支配しようとしていることはたぶんに多い。子供が親を見てきめれば良いという基本姿勢を持ちながら、助言すれば良い。
割合大人になりと、子供からすれば、どちらかというと、父親でも母親でも我がままなほうが可愛く見えてくる。家は父親が本当に我がままで、小学校の教師をやっていたから、いつも子供みたいなことしか言わないし、友だちに「Aちゃんのお父さんは早く帰って来ていいわね」と言われても、「お父さんと一緒だとニ時間も御飯を食べさせられるから嫌だよ」と言っていた。自分や弟は、大きくなると父親と御飯を食べるのは苦痛だから、2階に上がろうとすると自分の論理が始まる。「お父さんが今話しているのに、お前達が立ってどうするんだ」と始まって、「そんなこと言ったって、毎晩聞かされるほうはどうなのよ」と言うと、「お父さんは働いてきているから当たり前なんだ」と言う。それを聞くと、いつもこんな我がままな父親は世の中にいないと思っていた。小学校の先生は、いつも理想論ばかり言うが、「そんなこと言っても絶対違う」と逆らうと怒られる。弟も父親もやり合っていて、二人が近付くと今日はバイオレンスが起きるかも知れないと思っていたが、母親はすごく淡々としていたから助かった。母親がいなかったらどうなっていたかと思うが。しかし、大人になると、今自分が考えていることとかは、父親の方が分かってくれる。すごく心が通じている。母親は普通のお母さんだから、口では言わないが、女として普通の生き方をして欲しいというんのが、多分どこかにあると思う。そういう意味では、すごく母親に心配を掛けているとは思うが、父親は、自分の考えを言うとすごく喜んで食い付いてくるし、そういう意味では、自分は父親に似ていると思うし、父親の方が気持ちを分かってくれるし、自分は母親には似ていないが、母親としてはすごくいい母親だとだんだん思えるようになってきた。だから、夫婦はやっぱり違うし、親子も大人にならないと分からないと思う。
自分は、自分の父親がものすごく強いという思いがすごくあったから、父親のように強くなりたいというのがあった。酔ってマンホールに落ちた話しとか聞いていたので、雷がなって夕立ちが降ったりすると帰宅するまで心配は心配だったが、酔って帰ってきた父親を引きずっていた。それは、心の底に強い男だという意識があるから、どんなことがあっても、このおやじは肉体的に自分のことを守れるだろうという感じを受けていた。
父と娘は異性だから、そのへんが違うような気がする。
父親を通じて見る枠組みというものがある。例えば、家とか家族とか、そういう意味で、男だから女だからというより、長男だからというのもあるのではないかと思う。
家の作り方は似る。役割ということも一見違って見えるが、結局現代風にアレンジするとこうなってしまうというのがある。家の父親はあの年で料理とか何でも出来たが、それは家族の枠組みを示していたと思う。
大人になると自分が親になっていなくても、親の体現だったことが想像がつくから、やっぱり親はありがたい。
自分が親から受けた嫌な体験は、改善して自分の子供にやってみたいという思いがある。そういう意味ではすごく子育てしてみたいと思う。
うちは全然教育ママではなかったから、もしそうだったら、自分はどんなんだったかなと想像すると面白いが、自分は確かに教育ママにはなれない。
子供に自分の明確な理想像を持ち出して子育てすることは、本当によい作用をするのか。
それは育児が哲学として成立するために、医者はものすごくものを深く考える作業が必要であるが、母親は考えていないからこそ、育児はこういう意味なんだと教えていかなければならないほど大変なのではないか。先天的にそういうことを分かっている母親は当然いるだろうが、父親はそうではないだろう。かえって、不良でヤンママの子の方がものの考えがしっかりしているというのがあるかも知れない。
うちは親父がぐうたらで我がままだったから、母親は息子だけはなんとかちゃんとしようという思いは強かったから厳しかった。小学校5年生の時に悪たれついて「死んでしまえ」と言ったら、本当に死んでしまったので、自分としては真っ青だった。
親として、人非人みたいなことをしてはいけないと思う。最近、医学部の同級生にあったが、整形外科で偉くなるよりも、子供に対して後ろめたくない生き方をしたいと言っていた。
自分は「正しく生きるんだ」という時の、「正しい」ということの定義が人によって違うから、結局、禅問答のようになってしまう。それでもそれを分かるように、現代風に作っていかなくてはいけない気がする。逆に、ちゃらんぽらんにやっている親の子の方がしっかりしている場合もある。そうすると、その親はちゃらんぽらんそうに見えて本質を掴んでいることになる。言葉で表現するのは難しい。だから、例えば、治療と似ている。この薬は効くが使い過ぎるどうのこうのといくら言っても、正確に言ったことにはならない。なぜなら、患者の観察ということがいるからである。薬一つを出すにしても、実は哲学的に出さなければならない問題である。それが結果として、一番よい結果を生むだろう。それで答えがあるかと言えばない。
それは、養老先生が言っていたことと同じである。ああなればこうなるという公式は子育てには当てはまらない、なぜなら、子供は自然と同じだからである。
後ろめたくないというのが、その時間違えていても、自分が正しいと思って生きて、あとで反省ができる余裕が残っている生き方だったら良い。
自分はそれが結構大きなポイントかなと思う。自分がやった行為に対して本当に良い結果を生んだかどうかを常に公平な眼というか、真実を見て、もし間違っていたら自分の行動を変えていこう思いを続けることが一番大切なのではないか。
ある意味で、自分で抑制をかけることが大事なので、やってはいけない事や踏み越えてはいけない線がある。
西陣の生まれの山城しんごが「◯◯乞食」という本を書いたが、赤ヒゲのような医者の父親が、びっこの人の真似をして後ろをついて行ったら、父親は杖で思いっきり彼を殴ったらしい。つまり、これだけは絶対許さないものを持っていた。自分も息子を1回だけ怒ったが、一線を越えてはいけないというものを持った怒り方をする人はいるかも知れない。単に盗んだとかそんな事で怒る事はなくても、この一線を越えたら許さないと。
5歳の時に息子を怒ったのは、同じ年齢の口が狼みたいに裂けていた子が初めて世の中に出て、息子と出会って、握手をしようとした時に、息子は手を引いた。それで、家に帰って正座をさせて叱った。「もし手を握れなければ、お前は一生手を握れなくなる」と。次に会った時にはちゃんと手を握れた。自分もびっくりするような顔をしていたから、5歳の息子にしてみれば、それは恐かっただろう。ただ、それを一度許してしまうと、二度と彼の言葉の中に、何か大事なものが欠けてしまう可能性があると思ったから叱った。それ以外、自分は彼を叱った事はないから、あれは大事だった気がするし、彼も永遠に覚えている。昔の人は、そういうところがきちっとしていて、あとはわりと大雑把だったのかも知れない。
アメリカで、四人天才の子供が生まれたと特集していたが、これは生まれても良いかなと思ったのは、父親が帰宅するとお腹の子供に向かって、「今日は◯◯の話しをしよう」と言って、一生懸命話しかける。それを嫌がってやっているのではなくやっている。結果として、天才と言われる子供にはなったが、あの父親は、なろうがなるまいがやり続けるだろうという感じはした。
子供を面白いもの不思議なものとして見ている。だから、声をかけて意志を伝えたいとか、反応を見たいとかというふうに見ている訳だから、犬を観察しているのと同じ。自分も「犬ッころのようにこの赤ちゃんは可愛い」という言い方を時々するが、「犬と一緒にするな」と言うかもしれないが、実はそうである。人間は犬なんて分からない。その犬の子程可愛いというのはとってもすごい誉め方である。