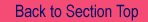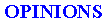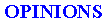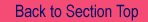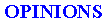
第112回哲学研 春 2002.3.19
春はそんなに花の印象が強くないと思うがどうか?写真を撮るなら秋の方がはるかに良いし、花屋に並んでいる花があまりにけばけばしくて、しっとりとした清楚な花がない。チューリップがそういった感じが少しするくらいで。確かに桜をのぞけばチューリップくらいしかない。実際には桜が散ってしまうと何もない、あとは緑の五月を待つだけという印象がすごく強い。花を撮ろうと思っても、近づいて撮る花は夏から秋の方がはるかに多い。
自分は春というとレンゲを思い抱く。だから、サクラソウもそうだが、小児科の中庭のダイコンの花や菜の花のように、一面を飾っているところはそうであろう。だから、やっぱり作られていないところの方がきれいである。
自分は最近全然見る機会が無くなったので何とも言えないが、花もそうだが、子供の頃よく土筆を見て季節感を感じていた。だから、群れているというか、遠くに菜の花畑が見えたりとか、例えばピンク色のサクラソウがある程度あるとか、レンゲの花とか、そういうのに春を感じる。山に行けばスミレだが、ただスミレは春から秋にかけて咲いているから、春だけ特徴的というような感じではないから、確かに、自分も小さい頃には土筆を見つけることが春を見つけるという感じはあった。 春は結構花が強制的に目の前に出されている感じがする。本当は木々の緑の五月の方がはるかに被写体としては美しい。桜のように霞んだような感じでボーと明るいというのはなかなか絵になりにくい。あと、花屋の花があまりにけばけばしいというか、秋の花の方がまだしっとりするところがあるのではないか。
今は秋でも春の花を売っているし季節感がない。ただ、桜に関していえば、春の代名詞とも言えるが、今年は例年より12日早く開花したということで、まだ準備が出来ていないのに、無理矢理春を押しつけられているかなという感じはする。
自分は田舎の昔のことを思い出すと、田圃や土手で見た春をこの辺ではあまり見ない。いや、東京でも小さい頃はヨモギとか取りに行ったし、芹とか取りに行ったし、自分の家の近所の清瀬の方はまだ生えているが。
京都の春は秋ほどではないでしょう?いや、春の円山公園の桜はきれいだし、鴨川沿いの桜もばっと咲く。だから、光景として全体像が見えるような美しさであり、華やかさがある。花一つ一つの美しさはないが。
桜は原生種か?山桜は確かに野生なんだろうが。有名どころの大きな公園とかに桜があるというのが当たり前に感じるが、人の手が入っている。
もう10何年前に亡くなった富山県の国鉄のバスの運転手か車掌さんが、悪性リンパ腫に罹って、元気な内に桜の苗木を買い込んで一本ずつ植樹していった。
自分も国鉄職員の人の話を見たとき、自分も何か生きてる間にみんなが見つけられないように一つ一つ何かをやりたいと思った。誰も知らないうちに、気が付いたときには全部桜になっていたとか。
中庭の桜だって10年であんな立派な樹になるということは、植樹してそんなのが完成するのは20年も30年も先ではない。ダイコンの花はあまり関西では見ない。あれは関東の人が大連から持ってきた種を電車から蒔いて、国鉄の鉄路のそばにずっと咲いている。自分が春で一番きれいな花だと思っているのはダイコンの花である。今年はダイコンの花がすごく後退したが、椎の木の枝が切られたときに、ダイコンの花の種が途中でならないままに終わったから、一番うしろまで追いやられている。しかし、実はこれを毎年繰り返している。後退しては前に出たり。だから、多分来年は前に出てくるだろう。
春休みはどんな感じだったか?あまり春休みは夏休みや冬休みほどの印象はないだろう。短いし、イベントもないし、何かつまんなかった。逆に宿題もなかった。自分は、父親が帰ってくるのが春休みが多かった。だから暑苦しいときに父親がいる。
欧米では夏休みのあとが新学期だが、これはどうも日本人の感覚にはフィットしない。寒い冬が開けて桜が咲いて新学期が始まるのが自然だと思うが、何で欧米人はあのスタイルで勉強を始めるのか?
それは春が遅いからだろう。ヨーロッパでは5月から春が始まり、6月にはもう夏になっている。日本のこのくらいの陽気だったら、向こうではきっとタンクトップを着ている。紫外線がきついからかなり焼けてしまう。春のぼやけた感じが日本人の心とすごく合っている感じがする。歌の詩もヒバリが鳴いたりとかは5月からである。それぐらいヨーロッパは4月ぐらいまではかなり寒いのではないか。日本は春の歌が多い。春はうきうきして嬉しい。まっているという操作が春だと思う。寒いけどちょっと温かくなって、早く春が来ないかなと思っている時期が一番楽しい。
向こうの受験はいつ頃なのか?入試は6月頃だろう。それはキリスト教のいろんな行事に関わっているのではないか。クリスマスがちょうど学校が始まって三ヵ月後ぐらいにあると良いかなと思うし。
日本の大学と世界の大学で比べられるのに、日本の大学は入るのは難しいが出るのは結構簡単で、逆に、世界の大学は入るのは結構簡単に入れるが、出るのは難しいという話しを聞いた事があるが、そういう意味で、日本ほど受験という悲惨さがないのではないか。フランス、ドイツは共通一次みたいな全国試験がある。アメリカもマークシートの試験があって、高校の成績が加味される。だから今の日本はアメリカ型に変わってきている。だから、コロンビア大学といっても、普段の成績とかボランティアやっているとか、そういうのでいっぱい成績がつくと簡単に入れる。出るのが難しいというのではなく、多分レポートとかの量がものすごくあるのではないか。だから、アメリカに行ったら分かるが、ボストンからニューヨークに行く列車の中でずっとレポートをあぐらをかきながら書いている女の子がいたから、普段もずっとレポートを書いているだけではないか。難しいのではなく大変なんだろう。
それに、アメリカとかは殆ど寮生活で、大学があるところにいろんなところからみんな集まってくる。だから、勉強でもさせておかないと危ない。日本は医学部だって、今だったら完全にマークシートである。卒業するのが難しくて立派な人がたくさん出ていたら、アメリカだってあんなめちゃくちゃな国にはない。
ヨーロッパは階層社会だから、エリートが大学に入って、大事にされるほんわかした世界があるのではないか。アメリカみたいに即座な結果を求めたりはしないと思う。そうでないと、ゆとりのある頭の良い子を育てられない。
大学の進学率を考えるとどうか?単純に比較は出来ない気はするが。アメリカと日本の大学生の比率は非常に高い。短大以上なら7割ぐらいだろう。フランスになると大学生は3割ぐらいかもしれない。アメリカも農村地帯になると5割くらいかもしれない。だから、本当に勉強する気のある人間は大学に行く。
しかし、秋から勉強がスタートするというのはどうもしっくり来ない。今日のテーマは春だが、総じて春になると新しい事を始めようという気になるが、その時に入学があったりするのでしっくりするが、欧米だと9月からスタートで、なんかしっくりしない。しかし、夏休みを遊んで、「さあこれから勉強するぞ」というのはそれはそれで分かる。だから、夏休みの重さと意味が違うのではないか。その意味では、日本の子供は夏休みは宿題がいっぱいあるが、春休みはないが非常に短い。しかし、勉強の嫌いな人間にとっては、夏休みが真ん中にあるのはラッキーという感じがする。
小学生の頃、終戦記念日とか原爆記念日とかに、せっかくの夏休みでも登校日で呼ばれて登校した。九州は日教組が強いから、自分も8月6日に登校して、原爆の落ちた時間に黙とうをしていた。あとは8月21日ぐらいに、他の県は知らないが、水泳大会とかがあった。当時は原爆が落ちて三十何年目ですとか言っていた。「夏の友」という夏休みのドリルの宿題に書いてあるとみんな知っていた。それは東京にはなかった。地方は、「夏休みの友」と読書感想文と自由研究とラジオ体操の出席が宿題だった。東京は、国語のドリルとか算数のドリルが別々だった。教科別のドリルだったら、頑張れば一日で出来たが、「夏休みの友」は結構ひねくれていた。例えば、天体観測をしたり、家族で旅行に行った感想を書いたり。お母さんと買い物に行ったときの金額を計算しようとかいうのが、算数の問題だったりする。たち悪いのは、それを一週間つけてみようとか。富山では今でも使っている。
それを真面目にやっていればいいが、それを遊んでいて最後の一週間でやろうとすると、捏造の世界になる。「夏休みの友」は小学校6年間続いた。自分は東京だが、5,6年生のときは宿題は一切無かった。だから、ドリルの方が努力の跡が見えたり、形がつくから楽だ。
自分(東京)の弟の学年からは、小学校に教科書を学校に置いていくものとなった。ゆとりの教育世代で、家で教科書を勉強しないで、ランドセルではなく肩からかけるうすべったい鞄を持っていっていた。小学校5,6年になるとランドセルがぼろぼろになって、うちのほうは、格好をつけて中学生が使うような鞄を持っていた人はいたが。うちは、必ずランドセルを持ってくるようにと言われた。そういうのを聞くと、東京から試されて、東京から学力を低下させられているような気になってきた。東京の人間は、基本的に学力のベースが高いだらう。
担任の当たりはずれと言って良いのか分からないが、熱血教師みたいなのに当たってしまうと、通常のカリキュラムにないようなミニテストをやりたがる。そうは言っても、テストは教える側からすると簡単である。ただ書かせて回収して採点するだけだから、あまり努力はいらない。自分の時は、札があって成績順に並んでいた。今から考えると、すごいことをやっていたんだなと思うが。自分の所は、中学の時に、県知事が来て成績のいい人を表彰していった。今でも、富山県では学力を向上させると言って県知事がやっていて、うちの県から何人東大に入った、何人京大に入ったと、中学、高校に回って言っている。自分も貰ったが、今から考えると、一種異様な雰囲気があった。
東京の人間は国語力は高い。経験が地方と全然違う。言葉だけではなく、まずは、田舎に暮らしていると電車に乗ることがない。それだけで人と触れ合う経験が違う。絵や音楽小説にしても、基本的にはコピーしか見ることがない。東京にいたら、本物を見ているから、格好を付けているわけではなく、元々小さい頃からセンスが培われてくるんだなと思う。ただ、数学の能力に関しては、地方の方が高い。地方の方がこつこつやったりする根性があるから、日本全国で統計を出すとはっきり出る。国語、英語は間違いなく東京の方が上である。
男女交際は、絶対地方と東京で格差が大きい。自分は、フォークダンスの時手を握れて嬉しかったのを覚えている。それに、もう高校生の時に使っているお金の額が違う。東京はそれを使う場所があるし、どうやって手に入れるかを知っている人は知っている。自分の所は、40分電車に乗ったらボーリング場が一つあるくらいだった。交通機関をわざわざ使って、街の中心部に行ったら数階建てのデパートがやっと一つあるかどうかである。
もし、地方で援助交際を実際やっていたとしても、小さい所だから、隠しておかなければいけない社会である。東京で流行っていることを地方の人が真似をしている。例えば、バブルの頃のディスコのお立ち台で踊るのを見て、地方の女の子は刺激されてワンレンボディコンを真似する。だから、地方の女の子の方が18歳ぐらいになると絶対東京の人の方が地味だ。自分がきれいな人だなと思うと、みんな地方の人だった。ワンレンボディコンが富山で流行った頃は、もうバブルが崩壊していた。東京では既に別なところに向かっている頃に、地方では報道され、定着する頃にはもう既に東京では終わっている。
大阪というところは、全く東京を意識しない。東京が今の話みたいな場所にならないで、完全にブロックしている。大阪は自分が一番だと思っている。それは都会だからである。東京の人が、例えば、そこそこ大きい仙台や名古屋の真似をしようと思わないのと同じくらいのプライドがあると思う。すごく面白かったのは、19歳くらいの頃にバイトをしていたら大阪の子が入ってきて、自分たちは全然意識していないのに、彼女はいきなり「あたしさ、本当に東京の人たちってやなんだよね」という言い方を、話したこともないのにしていた。今考えると、大阪は自分たちが都会だと思っているから、そういったのかと思う。それは都会だというのではなく、反東京意識であり、子供にまで及ぼすほど親たちは「東京なんか見るな」と伏せている。京都は京都で独自で、京都は大阪とは違うと思っている。潜在的には、京都と大阪と神戸は皆仲が悪い。地震が起きても絶対助けに行かないし、実際行かなかった。
どうして、東京の人間が絶対履かないようなピカピカの黄色にラメとか、大阪と神戸は靴が派手なのか?神戸は地味である。ハイソな世界と横浜の下町と同じ様なところが一緒に混ざっているのが神戸である。女性が早死にするのは大阪が一番というくらい激しいから、意地でもああいう格好をするのではないか。しかし、反面、経済感覚はすごくしっかりしているから、すごい派手だが実はお金はあまりかけていないみたいなところがある。東京の人間は、高いものを高いなりに着ている人が多い。
大阪の女を嫁にするのはなかなか良い手ではあると思う。知恵もあるし、ちょっと距離は置いていてくれそうだし。その代わり、確固たる自信があり、全体的には完全に抑えられているが。九州も男尊女卑みたいな格好して、女性に押さえつけられている。九州は圧倒的に女性が強いが、その強さと大阪の強さとは違う。大阪の女性はちょっと引いている。強気に見えても、ちゃんと旦那を立てるというのは九州よりは強いのではないか。九州は頭から三つ指をつきながら、がっちり財布の紐を握っている。田辺聖子の世界ではないが、「うちのお父ちゃん、アホやから。それでも、お父ちゃん、好きやねん。」この二重の言い方、人を馬鹿にしておいて、しかし、可愛いと言ういわれ方で夫婦が成り立っているような世界である。自分は、それはすごくいいなと、田辺聖子の小説を読んですごく思った。浪速恋しぐれの歌を聴いていて、あれはむしろ九州に近いんではないかと思った。だから、おそらく大阪でも、元々古い地域はそういう所があるかもしれないが、下に広がれば広がる程、むちゃくちゃである。大阪は、闘うという点でもすごいいい加減なところがあるから、さっきの原爆の話でも、大教組はあまりそういうことはやらなかったと思う。兵庫の方がもっと怖いというか、兵庫県教組は差別問題とかをやっていたが、大教組は教師も大阪人だから、どこかいい加減である。堺とか岸和田に行くと、すごくアグレッシヴではないか?岸和田は田舎で、もう和歌山である。大阪というのは、大阪市とその近域を大阪というのであって、堺まで行くと阪和線になるから、和歌山に近いという印象を持たれる。
考えてみたら、そんなに広い地域ではないのに、文化がはっきり分かれているのはすごい。東京だったら、山手線を中心に方向でわかれて色づけはあるが、ここは何ここは何というところまではない。それは、地方からの流入があまりに多いから消されてしまう。大阪でも北が神戸と京都に隣接しているから、大阪の北の方に行けば行くほど上品になっていく。南に下がって天王寺より南に行くと田舎者ばかりになっていく。自分は大阪の南の出稼ぎの人ばかりが集まってくるところにいたから、友達でも何でも一過性の人が多かった。
今、東京と大阪の話をしているが、都会というのは一回会った人とまた会うことがない。例えば、援助交際した人と街で会うことはない。そこで、自分とそこの地域を繋げているのは、ある意味文化かもしれない。しかし、田舎だと援助交際したらすぐにばれてしまう世界である。そこではよほど腹据えてやらないといけない。何かをやって「こら!」と怒られたときに、次の日には広まっている大きさしかないような所である。自分とかTさんは、大阪でもそういう人のつながりを嫌がるタイプの人間だから、はじめからここから出ることを考えている大阪人である。心斎橋のきらきらして世界はきわめて孤独な世界で、行き交う人も知らない世界である。しかし、戻ってきて自分の地域に住むと、誰がどうのこうのという世界になる。それには拒否感が強かった。そこにどっぷり浸かろうとする大阪人もいる。修学旅行で東京に来ると、バスに乗っている彼らは東京の悪口しか言わない。
自分の修学旅行は、鹿児島からわざわざ飛行機を使って尾瀬に行った。初日は日光に行って東照宮をお参りして、そこから尾瀬に行く。とにかく3日間歩き続けだった。その時は、音楽の先生が主任で、「君たちにも水芭蕉を見せてやりたい」というので尾瀬になった。帰りは東京から飛行機で帰った。修学旅行というよりも林間学校だった。理由があるとすれば、日本中から集まってきているから、家に帰るだけになる人間がでる。ジャージで歩いて、ゴミも自分たちで片づけることになっていたから、最後の日にはゴミの大きな袋を担いで帰っていった。
勉強以外の情報量は、今は別だろうが、昔はそんなに多くなかったが、一つ一つの体験は貴重だった。映画一つにしても感動だったし、今見る映画と自分の中では全然違う。映画でも、東京だったらいくらでも選択肢がある。自分の所は一軒だけ街に行ったら映画館があって、午前中が東映マンガ祭りで、午後からはだいたいその時に流行っている、スターウォーズやE.T.などのメジャーなやつを半年遅れでやっている。だから、コマーシャルで全国一斉ロードショーと書いてあっても余所の話だった。それでまず、マスターテープが来ることはなかったし、一本だけのロードショーも見たことがなかった。その代わり、南極物語とE.T.の組み合わせとか、二本立てもなかなか面白い組み合わせになるが。おそらく、ある程度早めに予約はしているのだろうが、フィルムが来た順にくっつける感じなのではないか。
自分がびっくりしたのは、徳之島にも8軒の映画館があったことである。ほとんど、相撲の朝潮のニュース映画をやっていたみたいで、映画が全然違う意味を持っていて、テレビの役割を担っていたのだろう。
映画のビジネスは、こちらから持っていった券を切って、切ったものを映画館が配給会社に持っていくと、前売り券の場合は半額返してもらえる。だから、例えば千円の映画だったら、半券を配給会社に持っていったら一枚五百円で買ってくれて、配給会社としては一枚千円の券を売って、半券が戻ってくるから合計千五百円の売り上げになる。当日券の場合は、全額映画館の収入になる。そういう取り決めがあって、政治家の資金源になることがある。どういうかと言うと、売れなかった映画を埋め合わせのためにだいたい田舎に持ってくる。映画館を経営しているのはだいたい建設会社だか、券を捌ききれないから下請けに回すが、下請けの社員に配っても誰も見に行かない映画がある。そうすると、もう少し知恵の回る土建屋が回ってきて、その券だけ全部切って映画館に持っていって、「二百円で売ってやる」と売り歩く人間がいる。それが、一昔前はうちの選出の代議士の選挙資金になって問題になっていた。
話を春に戻すが、自分の人生は春で決まった。夏が終わって入学していたら違っていたかもしれない。夏にめいっぱい遊んでから入学していたら、勉強していたと思う。入学してあっという間に夏休みが来て、やっぱり、今年もダメだったと思う。五月の連休が一つの節目ではないだろうか。四月はみんな一生懸命学校に通う。東大の学食も連休までは込むが、明けたらガラガラになる。出席を採らない授業には出てこないし。やっぱり、大学より東京に出て来れた喜びが満ちあふれるのではないか。まだやっていないことがいっぱいあったと思って、学校はいいやと思うのではないか。孤独感にさいなまれないで済むのは、人がいて明るいところが山とあるからではないか。入学してすぐに秋が来て寒くなったらかわいそうだから春に入学するのではないか。
四月に入学というのは、日本ではいつから決まったか。最初の高等中学校ができた頃は九月くらいではなかったか。初めて人と会うときも秋から始まったら、一目惚れもなさそうだ。春は間違えやすい。公立の学校を作っていく過程では、予算が締められるのが三月と八月だったのではないか。いや、もしかしたら、稲刈りと関係があったのではないか。九月には人が集まらないが、四月だったら人が集まるから。台湾、韓国も四月からだが、日本が持っていった制度をそのまま流用しているからである。台湾だと、良い中学良い高校の場合は、9月始まり9月終わりである。良い学校の場合は、卒業後のアメリカ留学を想定している。9月始まりの方が、うきうきしないで引き締まるのではないか。