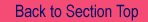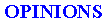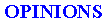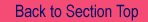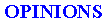
第113回 哲学研 給食について 2002.4.16
京都の給食は全然のーまるで庶民なメニューで、京都らしい給食は出てこなかった。ひな祭の時に菱型のお菓子が出たくらい。大文字の時は何も出なかった。主食は基本的にはパンで、週1回だけ水曜日に御飯が出るのが小学校四年生から始まった。パンは殆ど食パンで、たまにコッペパンが出た。給食で記憶に残る味はあまりないが、たまにプリンが出てすごくうれしかった。自分は食に対するこだわりがあまりないから、家の食事も覚えていない。京都の人間に対してみんな幻想を抱いているみたいだが、毎日京野菜を食べているわけではなく、普通にカレーライス食べたりスパゲッティーを食べたりしていた。母親も食に対するこだわりはない。父親の酒の肴を作る母親は、結構料理をうまくやらなければいけないが、うちの父親はお酒を飲まないので、食事にもうるさくなかった。栄養のバランスにはうるさいが。
Nさんと年代的に一緒だというのもあるが、小学校四年生の時から、週一回だけ御飯給食が始まった。京都と大分では離れているのに一緒という事は、国家的指針があったのではないか。コッペパンと汁物とおかずがあったが、御飯給食が出始めた頃はうれしかった。パンとカレー、パンとシチューも美味しかった。パンの時にはビニールに入ったマーガリンかジャムが付いていた。自分たちは新幹線ハンバーグと呼んでいたが、温めるだけのハンバーグが出てきた。あと鯨が結構出てきた。牛肉や豚肉よりも給食では鯨の方が肉としてはメジャーだった。
自分(群馬)は、最初から食パンだった。コッペパンは週に一回、それも味のついているのが出たきた。殆ど揚げパンで味のついていないのは月に一回ぐらいだった。ビンの牛乳が小学校三年までだった。四年生から三角形のパックになった。月に二回くらい牛乳に入れる粉が出てきた。牛乳が飲めない子でもその時だけは飲めた。おかずで記憶に残っているのは焼そばである。中学校まで給食は自分の学校で作っていた。中学に入って御飯が出てきたが、御飯だけが給食センターから来ていた。学校に配送されるのは古米を炊いて持ってきていたので、臭いから嫌いだった。一日ジャーに置いたような匂いだった。バットを開けた瞬間のあの匂いは臭くて、「去年の御飯です」と言っているようなものだった。
うち(東京)は、御飯はパックになっていた。御飯と麺の日があって、麺はスパゲッティーとラーメンがあった。中学校は選べる給食があった。御飯かパンも一週間前に○を付けた。バイキングの日もあった。学校は公立だったが、◯◯の会というとケーキが出たりして、狂死も一緒に食べていた。揚げパンも砂糖だけでなく、きな粉とかチョコとか色んなのがあって好きだった。食べるものだけはすごく楽しみだった。自分は、給食と音楽と体育だけを楽しみに学校に行っていた。給食で嫌いなものはあまりなかったと思う。いつもふざけながら笑いながら食べていた記憶がある。でも、自分はあだ名がみかんだったので、みかんが出ると悲惨で、一斉に「共食い」とコールされた。だから、一度もみかんが食べれなかった。全然話しは変わるが、ずっと好きな子がいて、その事をずっと黙っていたが、誰かがその話しをしてしまった時に、自分はその話しを聞いて噴いてしまった。給食で嫌な思いではその二つぐらい。
自分(東京)は昭和26年生まれだから、大分事情が違う。給食を入れる入れ物も食器もアルマイトで、小学校の4年ぐらいまではずっと脱脂粉乳だった。非常にまずくて、牛乳の味はしなくてアルマイトの金属の匂いがした。御飯は3月3日のひな祭の時だけで、あとは全部パンだった。途中から食パンがたまに出るくらいであとは全部コッペパンだった。揚げパんも出たが砂糖だけだった。おかずがすき焼きで、主食が甘い揚げパンという取り合わせで、どうしたらこんなまずいものができるのかというくらいだった。担任の先生が一緒に食べていたが、給食の時間になるといつも不機嫌になった。それから、ああいうひどい事をして良いのかと思うが、絶対残していけなくて、食べ終わらない子がいると食べ終わるまで外に出てはいけなかった。自分の学校は実験校だったから、教育大の心理の人たちが偏食矯正をやりたいという事で、どうしても食べられない子供は、放課後大学に連れて行かれて心理分析をやられるから、本当に可哀想だった。
自分はその当時三重県に住んでいたが、給食が食べれなくて、幼稚園の時に残されて苦しい思いだった。今から考えると酒の肴に良いだろうが、ねぎぬたが食べれなくて、夕方独り残されて食べさせられた。でも、食べれなくて、ポケットに入れて帰った。肉の入っているのも嫌いだったから、カレーでもシチューでも入れて帰ってシミになった。偏食の塊だったから、肉も一口も食べれなかった。ソーセージとかハンバーグは食べれた。
自分の年代だと普通は中学くらいからだったが、自分は小学校から給食があった。子供の頃から体が弱かったので、家で牛乳を無理矢理飲まされていて、温かいのとか甘いのとか色々やらされていて、すごく牛乳が嫌いだった。学校行ったら、それこそ粉ミルクで、息をしないで一気に飲み干していた。自分が給食で一つだけ記憶に残っているのは、今で言うホワイトシチュウーだと思うが、マカロニとか一杯入っているシチューが好きだった。それで、今でいうナプキンを、みんながみんな持って行ったのかは記憶にないが、「頂きます」をするまで掛けて待っていたのが楽しかった。そのナプキンはビニールで出来ていたり生地で出来ていたりしたが、学校から支給されたか、持って行ったかは確かではない。お盆の代わりにこぼしても良いように使ったと思うが、それは小学校だけだった。
自分(奈良)のところは平凡な給食で、食パンとコッペパンしかなく、おかずも変わったものはなくシチューとかで、楽しみというと、パンにつけるチョコレートだった。休んだ人の牛乳も楽しみだった。あと、給食にどうしても汚いイメージが残っている。牛乳を噴きだして臭い匂いが残ったりとか、残飯のグチャグチャしたイメージが残っている。校長先生と一緒に班ごとに年に一回ぐらい食べていたような気がする。今から思うとそんなにたいした事ではないが、その時は総理大臣と会っているような感じだった。給食の味は殆ど覚えていない。
給食は大嫌いで地獄の日々の連続だった。肉はダメだから、カレーとかシチューとか見た瞬間にダメだから、配膳する時に、「入れるな」、「ちょっとだけにしておけ」とか、「肉入れないで汁だけにしておけ」とか言っていた。あと、最悪だったのは、牛乳も大嫌いだった。だから、まず牛乳を一気に飲んでしまって、それからパンを食べた。小学校の頃は残しても良かったから、結構残した。とにかく早く終わらして、みんなが食べている間に野球の陣地取りに行っていた。給食は良い思い出がないが、唯一あるのはチョコレートだった。給食が全ての授業の中で一番嫌だった。今では不思議なことに食べれるようになったが。中学校では弁当になったからホッとした。牛乳が大嫌いだったから、シチューの白い色のを見ただけで、「こんなもの食えるか」と言う感じだった。じゃがいもだけはパンで拭いて食べていた。大学には行ってこちらに来てから肉が食べられるようになった。それまでは、牛肉と豚肉を見た瞬間にダメで、唯一運動部をやっていた時は、試合とかの前に、肉を食べなくてはいけないと、脂身のない赤身だけをカチカチに焼いてケチャップを付けてやっと食べたくらい。あとは魚ばかり食べていた。とにかく、食べるものを選べなかった。自宅でも、漬け物とお茶漬けで良かった。東京に出てきて、定食に出て仕様がなく食べてみたら、初めて美味しいということに気がついた。脂身も切って赤身と一緒に食べたら美味しいと。母親が小学校の頃よくホルモン屋に連れて行ったが、見ただけで食べれなかった。だから、食わず嫌いだったんだろう。食べた瞬間口触りとかがダメで、飲み込めばいいのに飲み込めなくてずっと口の残る。流し込むのに牛乳しかないが、先に飲んでしまっているから悲惨だった。白いシチューが美味しいと思ったのも、大学に入って親戚の家に間借していた時に出されて初めて思った。
三年生の半年だけ大阪にいて、四年生からは神戸に行った。母親は初めから灘中に入れるつもりだったが、自分は、「あそこに行けば、髪の毛を切らなくてすむ」と、それだけを考えていた。母親は人間関係にうるさい人で、「世話になった人は裏切ったらいけない」、「お前の力で偉くなっているわけでも何でもないから」、「お前がこんなに勉強出来るわけがないんだから、私のお蔭でもあるし、塾の先生のお蔭でもある」と言われ続けていたから、「自分は頭が良いんだ」とか「自分は偉いんだ」とか思っている暇がなかった。ちょっとその気になると「何を偉そうなことをしているんだ」と、常に叩かれていた。
話しを聞いていると、自分(大分)の給食は結構原始的な給食だったかもしれない。原始的と言うのは、お盆もアルマイトのお盆だし、コッペパンが基本で、食パンがたまに出始めたのは小学校の四年か五年からだった。シチューもあったがチャンポンもあった。チャンポンといっても麺と野菜を一緒に煮ていた。箸が出たのは御飯給食が出てからで、それまでは先割れスプーンだった。良く考えたら、副食も殆どついていなかったが、思い出したのが、プリントかと同じ感覚でトマトが一個一人づつ出てきた。御飯給食よりもトマトが出る回数の方が多かった。御飯もやっぱり臭かった。あと、自分は給食委員になっていて、その会議に出ると「生徒の意見も教えて下さい」と聞かれた。給食のメインの食事は学校で作って、牛乳は業者が運んでいたが、10時くらいに運んできて日の当たる場所に置きっぱなしだったので、「こんな牛乳は飲めない」と言ったが、最初は聞き入れられなかった。そのうち親も「それはもっともだ」と言うことになって、学校と半年くらい交渉して、日陰に置くようになった。北九州は日教組が強くて、中津は炭坑があった影響で、そこだけは教師の側がが生徒の意見を言うことを聞こうという動きだったのではないか。
記憶がまだらになっていて良く覚えていないが、脱脂粉乳はかろうじて飲んだ記憶がある。自分(宮城)のところは、鯨の漁獲高日本一の石巻が近かったから、一週間に一回は鯨が出た気がする。カツと立田揚げとソテーと佃煮と。周りは「また鯨カツか」とか言っていたが、自分がシチューよりも好きだった。あと、さつまいもをマッシュポテトのように潰してレーズンを入れたものを、たまたま病み上がりかなんかの時に食べて吐きそうになってから、それ以来見ただけで気持ち悪くなった。
自分は、みんなで給食を食べている状景を思い出せない。これが嫌だったというものも全くない。トラブルを起こすことは全くない子供だったから、きっと言われた通りに食べていた。もちろん、コッペパンと脱脂粉乳だけで終わった気がするが、我々の時代には、今のコッペパンに挟んである焼そばとかハムカツとかがおかずだった。コロッケも薄くて丸くて独特の味のコロッケだった。多分その時に給食を何年も作っていた人たちが、パンにいろんなものを挟んで今食べているのではないか。自分の記憶では確かにシチューもあるし、もしかしてカツが多かったかもしれない。それは鯨かもしれないし。ただ、このとんかつが美味しかったという記憶は、ペラペラのとんかつで、その味がものすごく美味しかった。今見たいに厚い肉ではないが、それがすごく記憶に残っている。コッペパンに具を挟んで食べるのは日本ぐらいではないか。アメリカにはハンバーガーがあるが、炭水化物を挟むから基本的には違うと思う。コロッケも基本的には同じであろう。自分は、給食の状景を思い出さないのは難無く通り過ぎていたのだろう。当番の覚えもないし、トラブル起こした覚えもないし。だから、一人で黙々と食べていたのではないか。あるいは、家に帰ったらこうやるんだと思っていたのかもしれない。中学は、自分の時は弁当でないから、昼休みに家に帰って食べていたが、お茶漬けとコロッケに漬け物が定番だった。高校も弁当ではなかったのではないか。自分も弁当を人前で見せたいと思わないから。幼稚園は一ヵ月でやめた。教師が赤ちゃん言葉で話しかけてくるのが嫌だった。それに、歌に合わせて手をうったりするのが出来なかった。要するに、子供を子供としてしか扱わないのは嫌だというのがあった。五歳で人を差別してはいけないと思っている子供だから、そう思うのは当然だと思う。自分は先生の周りに集まる子供をうらやましいと思わず、だからといって、子供をばかにしているんでもなく、ただ、ああいう付き合いかたが嫌だなと思った。それなら自分一人の方が良いと。食べるということに印象がないのは、強制がなかったからだと思う。
自分は幼稚園に行くのは嫌いではなかった。保育園よりは自由に出来た部分があって、遊びを作るのがうまかったみたいだ。しかし、やっぱりみそがあって、自分は楽しくてみんなも付いてきて楽しく遊んでいたら、母親が幼稚園の先生から、非常に勝手なことをすると呼び出されていた。帰る時に「何やったの?」と聞くから、「こういうことだ」と説明すると、母親は「この子は悪くない」と分かったみたいだ。そういうことが何回かあった。問題児だった。何かやると「先生、おかしい」とやっていた。
自分は幼稚園の時、先生の言うことがさっぱり分からなくて、まず、山折り谷折りが毎日分からなかった。オルガンとかも弾けていたが、人前では絶対弾かなかった。あと、何でみんなが手を挙げているのかなと毎日思っていて、毎日幼稚園に行きたくなくてバスのところで泣いていた。
自分も確かに山折り谷折りが分からなかったし、右と左も分からなくなって混乱していた。
自分も小学校一年生まで右左が分からなくて、学校から帰ってきて「右と左が分からなかった」と言ったら、「あら、そう」くらいで済ましてくれるのかと思ったら、まじに怒ってご飯を食べさせてもらえなかった記憶がある。箸持つ手が右と言われれば分かるが、「右はどっち」と聞かれると頭が真っ白になった。向かって右と言われても、チンプンカンプンだった。
養老先生の言う『脳化人間』の始まりは、これが右という概念をバッと入れられることから始まるが、混乱する方が正しいのかもしれない。混乱をさせないような、小さい時からの育て方が必要である。昔は、小さいうちから右か左かを言う人間はいなかった。むしろ、即答型の形で子供を育てる方が危ないのではないかと思う。勉強はできるかもしれないが、日本のエリートがダメになるのはそういう理由であろう。
自分は学校で一言も喋れなかった。一年から三年まで同じ先生で、先生からは言葉を投げかけられているが、自分からは先生に声を発していない。三年の父兄の懇談会の時に、母親が「一度もお話をしてくれませんでした」と言われた。担任はすごくショックだったみたいだったと、大きくなってから母親に言われた。きっと今だったら落ちこぼれだろうが。
今だったら、そのことについて教師が攻撃してくるだろう。まず、自分が馬鹿にされていると思うだろう。昔の先生は馬鹿にされていると思っても、「仕様がないか」というところでおさめられるが、今の先生だったら、絶対喋らせようとするだろう。
馬鹿にされているとはきっと思っていなかっただろうが、喋らない子供だったから、一生懸命問いかけてほぐそうとするがだめだった。その頃、一クラスが50人位の人数で、自分の隣にクラスで一番の暴れん坊が座っていたが、彼は絶対自分には意地悪はしなかった。四年生からだんだん慣れてきたが、後遺症はずっと残っていて、学校で喋らないというのはずっと続いた。でも、聞くことは聞いていたが、仲間に入れてもらえず、ただ聞いていただけ。
今だったら、それをいじられる時代なのではないか。自分の小さい頃を考えると、放っといてもらって良かったと思うことがいっぱいある。
どこかつまずいていることを分かっていることが大事である。それが、今子供達に襲い掛かる画一さではないのか。ゆとりという名の画一性ではないのか。不良でも何でも入れておくしかない。人間はいろんな人間がいるんだし、一生喋らない人もいるかもしれないと思って教師をやっていれば、「まあ、そういうもんか」と思うだろうし、それで良いのではないか。どこかで許してくれるものが世の中にいつもなくてはいけないのではないか。
共通して言えることは、昔の先生は今の先生ほどは迫ってこなかったのではないか。今の先生は、すごくおっかなびっくり怯えてやっているからダメ。昔の先生は怒る時は恐かったが、普段はあっけらかんと接してくれた。今は親も騒ぐし、親も教師も同じスタイルで子供を育てている。