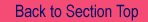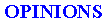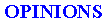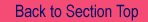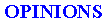
第114回 哲学研 マスメディア 2002.5.21
日本テレビの『めだかの学校』のドキュメントを見て、マスメディアがこんなに有効に使われたことはないと思った。取材した人の主観が入ったりとか、証言がうまく取れなかったりとかで、そんなにすごく良かったと思うことはなかったが、今回に関しては違った。これまでメディアの危ない部分を気にしているところが多かったが、何が今回良かったのか考えてみたい。
自分も知らなかったが、NNNドキュメントは20年続いている。だから、日本テレビの中で、あの制作部だけが徹底して真面目な路線を走り続けている。あの企画はフジテレビには拒否された。フジテレビは明らかに病院からのクレームが怖くてやめてしまった。フジテレビの番組を見たら分かるが、お涙ちょうだいで、マスメディアがあるイメージを、障害者なら障害を持って苦労しているとか、看護婦なら看護婦の番組をある眼を通して作っているところがある。そこに全部の意識を向けさせようという流れが今のマスメディアで、それとほぼ同じようにして、今の部分主義というか合理主義の流れが、「みんなはこういうふうに考えなさいよ」と言われ、そのままを受け入れて、現実の感覚のない、つまりどこか偽の部分、本音と建前の建前の部分だけを喋る世界を作ろうとしてきたのが、おそらくここ4〜5年の特徴なのかもしれない。その中で、ヨーロッパであんなに右派が台頭してくるのは、本音がある意味出始めることを認めていくぐらい世の中が歪んできている。あの番組は、相当熱心に30分枠を1時間枠にしたりとか、最後の場面を明るい場面で終わらせたりとか、ナレーションが男性ではっきりした口調で淡々とした特徴を持ち、しかも語っていることは本音だった。マスメディアの中にもそういう人間がいるということである。こんな不思議な出会いがあるのかと思うほど不思議な出会いだったのではないか。我々が弾圧を受けて、潰れるかと思ったがとにかく踏ん張って残ったことが良かったと反響にもあったが、ドキュメントを作る側にも危機意識がなければもっと甘ったるい作品になったのではないか。例えば、Mさんが撮影している時にも、婦長が来て邪魔するから隠れて撮ったりしたが、その危機感がすごく画面に出ていたのではないか。それが多分、今までの建て前と本音ではない形の番組になったのではないか。ああいうメッセージ性は今ない。新聞を読んでも、人の揚げ足取りや有事法制や、訳の分からない右翼の方針が出ても、実は何も解決はしていかない。だからみんないらいらしている。大蔵官僚を見ても、これで官僚ができるのかと思うし、みずほ銀行みたいにでかくなったらでかくなったで、権力争いにうつつを抜かして、コンピューターの故障を予想していたにもかかわらず、何もしなかったのはふざけている。だから、ああいうのはやっぱり虚構で、トップの人間は偉いというのは崩れていっているのに、その割に権力に弱い。あの番組は(東大という)中央中の中央の話だったから、そういう意味で衝撃はあっただろうし、自分自身も東大小児科というところだからやってこれた部分もある。
自分はMさんが苦手で、彼女は新人ディレクターだから、撮ってやるぞという気持ちがすごすぎて、いわゆる医療の現場が撮りたいという感じだった。本当に努力して本当に辛くて大変な現場を撮りたいと。最初に話を聞いたときに、拒否感を持ってしまって、本当は嫌だなと思った。そうしたら、Hさんというプロデューサーの人が来て、めだかの学校はどういうものかという話を何時間も聞いてくれた。聞いてくれたときに、良いところを撮ってやろうというのではなく、ちゃんとしたものを捕まえて撮りたいという姿勢が見えた。Mさんは新人だけれども、Hさんの言っていることを理解してきているというのが、月をおって分かった。最初の二ヶ月位はMさんが苦手で、彼女には撮られたくないとどこかで思っていたが、付き合っていくうちに、お互いが思っていることをどんどん言うようになったら、彼女がすごく努力してくれるのが見えて来て、それがすごく大きかった。この間女性のプロデューサーが一緒に来たが、彼女が喧嘩したと言っていたから、Mさんにすごく言ったみたいだ。あの会社は上で支えている人がすごいと思ったが、Mさんの良いところと悪いところを全部消化して、引っ張っていったのがすごく分かった。ナレーションでも喧嘩したと言っていた。Mさんは斉藤由貴で撮りたかったが、そのプロデューサーは男性が良いと、そこでも喧嘩になったみたいだ。最終的に出来上がったものはちゃんと重みがあって、最初にMさんに言われたものとは全く違うものになっていた。彼女と最初にあったときと終わったときでは、全く違う感性になっていた。自分はそれはすごく嬉しかった。最初から分かり合えてうまくいっていたら、こんなにいい番組にはならなかったかもしれない。合わなかったから分かり合おうとしたのかなと思う。展覧会の時も大変だった。要するに、自分にしてもAさんにしても表に出たくないし、ずっとそんなのは嫌だと思っていた。それは、自信が無くて意固地だからかもしれないが、彼女はやっぱり撮りたいから、どんな人にもめだかの学校のことを聞きてしまう。本当はスペースKに来たんだから最初にしなければいけないことは、Kさんに話をしなければいけないのに、若いし熱意がある分、そういうことも関係なしに、来た人に取材の意図も話さずに聞くから、みんなが嫌な思いをしてしまった。しかし、思ったことは言わなければいけないから話したが、ちゃんと聞いてくれたし、だんだん分かっていってくれているのが分かった。だから、出来上がったときは試写したときよりもすごいと思ったし、メディアの力がこんなに大きいとは思わなかった。
戦争写真家で有名なロバート・キャパの写真はすごく悲惨なのもあるが、戦争中の人の普段の生活を激写した。彼は受け入れられたと実感するまでは一枚もシャッターを押さないという信念を持っていた。その現場に行くまでは現場に対する印象はなんだかんだと言っても偏見がある。撮ってやるという熱意は、そこに魅力を感じなければいけないので、動機としては必要だが、いったん現場に入った後のメディアには、その現場をどこまでリアルに捉えるかという責任が課せられている職業だと自分は思う。こういうものを撮りたいからというだけで撮っちゃうと、やっぱりそういうものにしかならない。
取材ということ自体が、ある程度同化していくというか、自分の中で消化していくというか、そういう過程はどうしても避けられないと思う。ただ、それを本当に真面目にやるかというと……。
今までめだかの学校を採りあげた一番大きなメディアは『アエラ』だが、ただ、文章にしたものは伝わらない。見る側からしたら、あの淡々とした人動きの中に、めだかの学校が凝集している気がする。逆に、アエラの文章は細かく書いてある分だけ消えてしまう。映像という手段が、あるいは言葉がなかったことがかなり大事だったかもしれない。言葉では了解できなかった部分があったのかもしれない。だから、ナレーションも女性にというのを上の人が反対したのは、余分なものが入ると感じたかもしれない。
言葉に比べて映像の方がすごく手間がかかる。普通、200日も使って文章の取材はしない。
だから一人のインタビューにしても、わずか10分を出すために何時間もかけている。Aさんの倍も3時間ぐらいとったが、的確なものだけを使っている。あとは桑を以て耕していればいい。実際の言葉と行動とが重ね合うというのに1年くらいはかかる。
お互い取材する側もされる側も意識してしまうから、お互い何も気にならなくなったときにカメラが当たると、客観的な映像がとれるのではないか。
ただ、ものすごく明るく見えた中庭の映像は、Mさんが自分一人でしゃがみ込んで撮ったが、あれはもう完成したからである。あれは、本当の花を添えるという形で作り上げられたとき、彼女は何かを気付いたはずである。
最初に花を撮ったのと後で撮ったのでは、絶対違うだろう。
その花も手間をかけて、ついでではなく撮りに来る。それは、今の雑誌とかの取材とは手間のかけ方が違う。
気合いが入ってよく理解してくれた制作スタッフと出会えたことは、すごいことだなと思う。
やっぱり、向こうもこの世の中に対して同じ考えをどこか持っているし、日テレは日テレで同じ考えを持っていた。それが合わなければ、あの番組が1時間番組として展開はされなかっただろう。しかし、それが時代が必要としている問題ではないか。
何年か前、グルメブームがあったが、自分が大学にいたときの同僚が味覚の専門家で、関東地方では彼女しかいない。それで年中テレビの取材が来る。それは、インチキでひどかった。2回ぐらいディレクターが打ち合わせに来るくらいで、芸能人が来て本番になる。真面目さは全然感じられなかった。
映像の中身に関していうと、自分の友達からいろいろ反響があったが、一番言われたのは、もっとたくさんの人がわいわいでてくるのかと思ったと。
自分はMさんにすごく言った。まるでこれではHさんとAさんと自分だけで、しかも患者さんも3人だけでは、今まで撮ってもらった人に申し訳ないという話をすごくした。そうしたら、彼女には「プロデューサーに聞いてみないと分からないが、とにかく焦点を絞らないといけないので、いっぱい協力してもらったが省かなければいけない」と言われた。「でも、お願いだからもう一度話をしてみてくれ」としつこく言ったがダメだった。
自分はそれで良かったと思う。焦点が絞れていて、非常に美しいと思った。そこに向かってまっすぐに突き進む印象を受けた。余計な人が出てくるよりも、よっぽど良いと思った。
しかし、本当のことを言うと、自分は滅茶苦茶悩んでいた。人と取り持ったのは全部自分で、Mさんから誰々と連絡を取りたい言われて、「すみませんが、取材をさせていただきたいのですが」と全部自分がやった。だから、「自分はこれでは」と夜中に電話したが、彼女は頑として聞いてくれなくて、「私が説明しても良いんですけど、とりあえずプロデューサーに聞いてみないと」と言われた。知っている外部の人間には一応全部連絡を取って謝った。
そのことは、伝わっていると思う。押しつけが無くて淡々としていて、それでいて、すうっと心にしみてくるような。しかし、自分の友達がやっぱりちょっと動揺している。「何でN先生はもっと出てこないのか」と。
じぶんは、それが本音だと思ったから……。
しかし、こういう番組の作り方があるんだということを知ったという意味で新鮮だと思う。
Sさんにもさんざんインタビューをしたが、彼の言葉は入れなかった。それはわざとだと思う。たくさんの言葉を使ってしまうと、逆に言えば、攻撃的な姿勢が見えなくなるからである。あの番組では、自分の攻撃的な言葉が随所にあるようになっている。
Hさんはそういうふうに言うかもしれないが、自分は自分も半分Mさんと一緒にやったという気持ちがあって、「自分は出なくても良いから、他の人を出してくれ」と言った。自分ではこんなので良いのかなというのがあった。
患者のさんの中心はNちゃんにすると決めたから絶対ああなる。Y君にすると決めればまた違うから、みんな一人ずつそれをやったら1時間ではとても終わらなくなる。
もし、たくさんやって最後にまとめようとしたら、ものすごく陳腐なものになっただろう。
それに、ああいう活動が、今まさに流れの中でつぶされようとしていることに焦点を当てたいから日テレもやった。
ちょっと前にもフジテレビで同じ障害者の親の離婚のをやったが、それに比べると、Nちゃんの親の強さと、離婚をしても負けないで、一人で働いくことに焦点を当てたのはやむを得ないと思うし、そこを描きたかったと思う。それでY子ちゃんの親も一緒にというのは、単に神経の重病だけではない病棟の持つ意味も伝えたかったと思う。そうでなければ、普通亡くなった子供の取材を受けることはない。Y子ちゃんが亡くなって、毛髪のない写真を提供した。それはNちゃんとは違うここの病棟で生きていた象徴的な子供として入れた。
あれだけちゃんと撮ってもらえば、めだかの学校の活動がオウムだという噂を流して、何でもかんでも信じ込ませようとしていた彼らも発言ができなくなる。