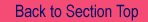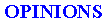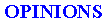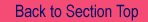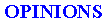
第115回哲学研 沖縄 2002.6.18
沖縄の音楽は沖縄にしかないメロディーなのか?海辺端で豊かな自然の中で暮らす穏やかな人たちが作ったものなのか?それはどこから由来しているのか?
奄美の音楽はすごく良い。
なら、なおさら奄美というところは、琉球王朝よりも薩摩に虐げられて歴史を持っているから、差別を何重にも受けた人たちの歌である。
ただ、音楽という意味では、かなり民謡と通じるものがあると思う。
通じるものはあるが、あのメロディーは違うのではないか?
多分、中国の音楽と似ていて、使っていない音が奄美の音楽にもあるはずである。確か、中国はファの音が使われていない。奄美はドミファソシドでできているのではないか?
それは気候と関係があるのか?モンゴルなんかの音楽は奄美のそれとは違うだろう。だから、土地柄と人々の心の穏やかさは何によって規定されるか。タイに行ったら奄美のような音楽かといえばそうではない。それなりの歴史を持っていないと、つまり、国というものが歴史の中に覆い被さっていないと生まれないような、村落の問題がいつも中央なり、奄美なら薩摩藩と琉球王朝の両方から責め立てられ生きている村落、しかも気品が高い。珊瑚の海があってそういう音楽ができるのか。それは、他の土地にはないのか。自分は日本のメロディーというか、童謡は素晴らしいジャンルを持っていると思うが、あれは何故で生まれるのかということが不思議である。西洋音楽を取り入れて、明治の終わりぐらいから童謡を作って行くわけだが、詩も見事で、子供のためにあれだけの曲を作った日本人は、すごいものだと思うが、それより以前に作られた島歌が、今アルゼンチンで流行っているのは何故か。
島歌は、南アメリカの人間にとってもすごく引かれる音階を持っているのか。南米には「コンドルは飛んでいく」という曲があるが、あれは半分移入ものを消化した曲である。
「コンドルは飛んでいく」もそうだが、アルゼンチンに行くと音楽が移入ものであるが、タンゴの前段階みたいな音楽があり、それは島歌に通じるものがあると思う。
他には島歌みたいな音楽を作っているところはあるか。アフリカは違うだろうし。東南アジアも違うだろうし。
しかし、東南アジアや韓国の音楽も非常にきれいである。
自分は北のルートなのか、それ以外のルートで作られるものなのかを知りたい。韓国には島歌みたいな音楽があるのか。自分は島歌だからこそ、統治されても海が周りにある統治のされ方と、陸続きで統治されているされ方では、生きている人たちが違うのではないか。それがメロディーに現れるのではないか。
自分は中学の時に黒人霊歌がすごく好きで、アパルトヘイトのこととか分からなくても、その音楽を聴くと自然に涙が出てきた。だから、奄美の音楽もそれに近いものがあって、理屈ではないと思う。
必ず国家が生まれて元々基調として持っていたメロディーが新しい音楽と接合する時に、純化されていくわけだろうが、それは個人と共同体というような世界の認識の仕方が、差別されたらされた悲しさがあり、それが歌に出る。ただ、あの島歌にはもっとポジティヴな部分もある。自分たちの生きている生き方が、穏やかで優しくて美しい世界があるんだという言い方をしている。
琉球の民謡は穏やかで飄々とした部分がある。奄美の民謡は暗くて激しい。
それは琉球王朝が支配を受けていず、穏やかな国造りが出来たからである。自分は、音楽ほど人の心を純粋に表現しているものはないのではないかと思う。
徳之島は確かにポジティヴである。平家が落ちてくるが、そこで隠れるのではなく、防衛するために生きている。神社とかが防衛施設になっていて、船の出入りが見えるところに建てられた。常にどこからか支配されようとするが、できるだけ自分たちの何かを残そうという意志が強かったと思う。だから、沖縄にもない一つの信仰心というか、宗教、習慣がある。
西村京太郎の初期の作品の中で、島というのはそういう描かれ方をしている。
自分は加計呂間島に行った時に、霊感はないがものすごくゾゾゾ〜とした。恐いとかではなく、精霊ではいけれどもここに何かがいるという感じがした。
それはただならぬ海の強さがあるからではないか。あそこは巨大な山があって、村落がへばりつくように島を作っていて、本当に平地は少ない。だからある意味恐ろしいところである。暗闇の大きな山と水平線が真っ黒に見える世界では、政治はないのではないかと思う。田中一村もその無気味さに惹かれ続けたのではないか。海の独特な感じが、まるで原始の、未だ地球上に生命が現れていないかのような思わせ方をさせる力が、琉球とは違ってあると思う。
自分は沖縄に行ったことはないが、奄美大島の自然は非常に豊かである。小さな日本みたいな感じがする。雨が降ったり時間時間で島の表情が変わるから恐い。神と語れる感じがする。逆に言うと、自分自身が持って行かれる感じがする。
だから島民は徳之島と比べて非常に知的な感じがする。徳之島はさとうきび畑があるぐらいで、非常に荒っぽい。島によって性質が全然違う。
Yさんはどちらに興味を持つか?北側の例えば津軽とかアイヌとか、あるいは南の島か?
自分はアイヌも沖縄も全く違う国のような気がする。自分たちは一応日本人だが、いっしょくたに日本とされているが、本当に沖縄という国がある感じがする。あと、アイヌの人とアンデスの人の遺伝子が同じという話しがある。
アフリカから北上してモンゴル高原に着いた猿の一群がモンゴロイドになるが、彼らが原住民の考えを作った。この哲学研では子供の哲学をやりたいというのは勿論あるが、子供の哲学というためには自分たちが子供の時の分析が出来なくてはいけない。それと同時に実は人類の子供である時期のたたずまいというか、ゴリラもそれに通じるところはあるが、あの穏やかさはどこから生まれてくるのか。おそらく彼らは、葛藤の上で酋長としての優しさを持ったのではなく、生まれつき優しかったのではないか。それが原住民の文明的ではない人たちの、本当の文化的なものの考え方ではないか。
自分はたまたまチリの人と親しくしているが、その人はスペイン人との混血という感じではなくアンデス系の感じの人。キリスト教も遮断するし、感覚としては日本人と同じである。その人も日本の三島由紀夫の感性が分かるという。
原住民の考えに一番近い宗教があるとしたらそれが仏教である。だから、こうとは決めつけない絶対の姿勢がある。腹を覚悟しなければならないというのが道元の考えであったが、アンデスの人たちにせよ環太平洋で生きていた人たちは、食べた動物から生きることを貰うためには、自分も覚悟して血の1滴も大地にたらさないようにして食べたり、それが覚悟という上で原住民が強く優しくいられる理由ではないか。日本人には覚悟が消え、文明化されたあるいは村化された言葉しか使えないが、言葉にならないものを持っているそういう人たちに我々が近付いて行きたいと思う。それが子供に近付く道でもある。
だから、沖縄は琉球王朝そのものがすごく穏やかだったのではないか。エジプトの紀元前4世紀の働く人の勤務表が見つかって、生理の日は休みとかが分かった。だから文明が進化することと分化が退化することはおそらく一緒なのだろう。ただある時期、西洋では18世紀から19世紀にかけては優れた人間の開花ということもあったのではないか。しかし哲学はそこで止まっている。
I教授が子供の為にと言っているやり方は社会主義の言葉である。要するに、勝手にやさしさの時には社会主義の言葉を使い、本音は自分はエリートだから資本主義では強者が弱者を倒してなにが悪いと言っている。だから今の社会は織りまぜた言葉、つまり己の言葉がない分だけ非常に弱い。今言ったような話しをしても映画を見ても、その記憶をとどめることが出来ない。うちの看護婦もそうだが、子供が死んで悲しそうな顔をしているが、病棟まで来れば笑っている。彼らは人間がやってはいけないこと、あるいはその感情を守らなければならないこと、最低必要限のことも出来ない。それは言葉を誰に対して使うかということだけで使うからである。己に対して言葉を使わないからである。
本当の優しさを伝えれば、相手が優しくない人間でも変えることはできるのだろうか?
それもどこかで逃げているから、言葉が他人と交わしているだけの言葉になって、実は本質は子供が憎い、この子さえ産まれなければという気持ちがどこかにある。きっと沖縄だったらその子ごと穏やかで豊かで入れたかもしれない。
自分も障害を持った子供を持ったわけではないが、持った感覚と持っていない感覚とは絶対違うと思うが。
自分は向こう側になった場合どうするかを考えるだけである。その視点でだけ親にものを言えることができる。親が体験している悩みは自分にはないが、今からそうなったとしてもあなたのようにはならないと。それが現実を生きる力や知恵になっている。それが哲学の力なのだと思う。20世紀以降は哲学がない時代が続いている。だから、島歌の中にはものすごく深い哲学があるというふうに思える。それは自分が感覚的に優しさの拠り所を知っているという意味である。それが奄美大島であれば、あの山々や海の深さのおどろ恐ろしい自然が生まれたばかりのような真っ暗闇の世界と、自分が生きているということはその世界と引き換えでしかないという覚悟を持っているのではないか。多分沖縄もそういう人たちが自分の法を超えなかったから、戦に人をかり出したりはしなかったのではないか。
沖縄は直接支配がなかった。経済的な打撃を被ることはあっても、日本人や中国人が現れて支配したというわけではなく、琉球王朝が上手く操作してきた。だから国という姿がなければ歌が生まれた。ただ、哀調は全体に自然が造り出したものであろう。奄美大島の場合はおそらく政治体制、つまり薩摩の支配が相当厳しかったのではないか。このようなことについて、自分は音楽としての学問として誰も書いていないのが不思議でならないが、ある地域をやれば量がそれぞれ多すぎてその分析に一生かかってしまうと馬鹿なことを考えるからであろう。和辻哲朗は「風土」で4つの気象条件を端的に言い表わしているが、それだけで良い。それを大胆に出せば音楽がどれだけ哲学的に質の高い意味を持つかが分かってくる。
陽性な琉球の匂いはどこから来るのか?
それは文明的なものではなく自然的なものだけでもなく、犯罪すら起こらないよう名小さな集落の中で生きていて、決して人を憎しみ合わないで済むようなものから生まれるのではないか。
自分は今の話しの中で欠けているものは、海で生きるということが欠けていると思う。何も見えない波を一つ一つ越えて陸地に到達するまでに、あれだけ力強い音楽がないともたないと思う。
だからそれが自然がもたらしている力で、海の力を超えなければ、つまり逆に言えば海の力を知っている人間が唄う歌なのではないか。月夜の海は綺麗かもしれないが、真っ暗闇の海ぐらい恐いものはないと思うが、日本人は文明によって海の恐さの認識を消し去っている。日本人には死をいつも前にして生きてきた時代が常にあったはずなのに、社会が密集して存在するために自然を隠してしまっている部分があって、それが今の弱さに繋がっているのではないか。アメリカ人がまだ強いのは、広大な大陸があるから強いと思う。
海で船に乗って一緒に生きるということは、後ろから蹴飛ばしたり狡いことをやっていたら生きていけない。意見が合わなければ納得させなければならないし、どうしてもダメだったら、取りあえず港に着くまでは仲間としてやらなければならない。
自分は、人間は文明から頭の中ででも離れて行かないといけないと思う。例えば、医局講座という非常に暴力的な仕組みで民主主義も確立してないが、本来は医者同士がプリミィティヴな穏やかな優しさで患者を包む世界を作らなければいけない時に、仕組みを持ち出してくる。だから、文明的であったりアメリカ的に進んでいるから正しいなんて絶対あり得ない。今冒されてしまっている村社会の言葉を拒絶しなければいけない。そして強さを自分なりの自然に求めなければならない。それが原住民なりゴリラに共感を抱くような考えを造り上げて、文明がなくても人間は立派だというところに到達しなければならない。いつも自由でいようとする、いつも自分の中で取捨選択出来る哲学を作らなければならない。哲学は常に方法であって、それを学ぶことが哲学研の中で一番大きいからこそ、子供にか子供のその子の哲学があると。哲学を持たない子供はどういう子供であるかといえば、言われた通りに親が喜ぶ姿を追求する子供で、潰れたらそれきりだが、上手く行けば偉いと価値観を塗り込められてしまう。だから何か事が起こればもたない。幸せを求めることも大事で、その幸せはどこから来るのかということも大切である。
養老先生が毎日新聞に投稿しているが、外務官僚は外務省という村の中でしか喋れない。つまり、この国はレベルが低すぎてトップ同士で付き合うことが出来ない。文学者と画家、あるいは文学者と政治家、実際に交流ができるかといえば出来ない。自分は実体験として、画家と一緒になった時どんな言葉を選んで良いか分からなかった。自分が分かってもらえるかどうかも分からなかったし、画家のことを理解出来るとはとても思えなかった。しかし、哲学研でいろいろ話しをして行く中で、良い画家は自分と同じことを考えていることが分かった。
それは利害の関係でないからであろう。利害の関係でない付き合い方をするのには言葉がいる。気持ちを持った言葉、その人間の占有の言葉、青いと言っても思い浮かべることは違うし、そういう意味で、言葉が自分のオリジナルである時だけ、村社会のレッテルとは違う言葉で話しができる。そうすると人を押さえ付けたりしなくても済む。例えば、医者と患者のことを考えても、常に医者という世界で使う言葉しか患者に投げ付けられなかったら、医者としては終わりである。
話しを元に戻すが、何故スイスでヨーデルのような音楽がうまれるのか、モンゴルの馬琴頭で奏でられる音が何故ああなのか、音にはものすごく深い哲学的な意味があり、千年の単位で蓄積された人間の感性と音楽が作り上げられることがすごく似ているというか、直細にその部分を表現している部分が多いのではないか。
沖縄と津軽で同じ三味線であるにもかかわらず、津軽三味線はすごく重苦しい曲が多くて切羽詰まったような感じがするが、沖縄はすごく楽しくなるような感じがするし、リズムが全然違う。
津軽三味線は冬の竜飛岬の感じである。死が直面していたり、自然が自分たちに被いかぶさってくる、そういう恐い中で、人間が人間として叫ぶような音楽になっている。
越前のごじんじょ太鼓は、あれこそ冬の荒海の感じがする。
民俗と音楽ということで、自分がすごく印象深いというのはどこかの国にあるか?
東南アジアのバリの音楽は流しているだけで良い。和みというよりちゃんとしなければという気持ちになる。お香を焚きたくなる。
小乗仏教は儀式に近いからその音色はあるのではないか。ある意味、天台宗とかのお経の揚げ方はそうであろう。
ロンドンデリーもそうだが、アイルランドの民謡が日本人にあるのは何かあるはずである。
地球の裏側にもかかわらずペルーの音楽も日本人に通じるものがある。
ルソーは「むんでひらいて」を作ったが、フランス人は子供の音楽を作っていたが、アメリカ人が来た時に恥ずかしくてシャンソンにかえたか。
音楽について誰かが分析しなければならないと思う。和辻哲朗が世界の気候を四つに分けたように、そのぐらいの分け方であっても、世界の音楽がどこから由来するのかを書く必要があるのではないか。メロディーとリズムがどういう理由で作られて行くのか。しかも、ぴったりとその地域に合っているということがふしぎでならない。
沖縄と津軽の三味線の音は、◯◯階とか当てはまるようなものがあるのか。
三味線の音ではないが、沖縄の音楽はドミファソシドでる。ドにミのフラット、ファにソ、シのフラット、ドである。だから、ドミファソシドの音を覚えれば、誰でも沖縄の音楽を作れる。
津軽の音楽にも統一されたものがあるのか。
音を抜いてメロディーが作られる。中国の音楽はファがない。
ということはもしかしたら、沖縄の音楽は一番最初は中国と同じで、あとから音を付けたのではないか。あとから抜くのは変だ。
駅で世界各国のCDを売っているが、そういうことをやるのは日本人しかいない。だから、日本人は比較的知識を持っているということだが、逆に言えば日本人にしか分析できない。タンゴを分析した人間がいる、沖縄の民謡を分析した人間がいると。しかし、誰も繋げられない。民族の本質の音楽の裏に一体何があるのかとは考えない。第一、ベートーベンにしても何故あの時代に生まれてきたのかも分からない。
その土地の自然があって、その自然から何かを感じた人間が作るということではないか。
自然が一つと、もう一つが社会。社会性が色こくにじみ出る、その時にジプシーの音楽だって生まれるし、アフリカの黒人霊歌だって弾圧がなかったら生れなかっただろう。もっと陽性な踊りで終わっていたかもしれない。
越前の方では、三味線は聾唖者の人たちが生活の為に各地を回って聞かせていた。
音楽は楽器が奏でるが、人間の声が先にあるわけだが、何故人間の声と楽器とが上手く落ち着くのかが学問的に見て不思議である。人間はドレミファソラシドで音楽をやらないはずである。歌といってももともと楽器で弾けるように作るわけではない。
だから、非常に大事な感性を一個人が千年生きて感じられるだけの重さは持っているのではないか。声から楽器に移るまでも千年くらいは時間がかかったかもしれない。