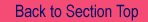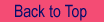「やっくんの瞳」刊行にあたって 児玉 容子
「やっくんの瞳」刊行にあたって 児玉 容子生後4ヶ月で東大小児科に入院した息子は、一度も退院することなく、この6月で16年目を迎え、今春、院内学級の高校生となりました。
入院当初、検査の段階から素人ながらも、単に検査入院だけではすまないだろうという、何となく不安めいた感触はあったものの、まさかこんな長期間、病室を我が家として生活を成り立たせる事になろうなどとは、正直言って努々思いませんでした。
ウエルドニッヒ・ホフマン病という病名を告知された当時を思い返してみると、親として不治の病である我が子をただ漫然と見守り続けていただけで、短命に終わるかもしれない息子のために積極的に何かをしようと行動したわけではなかったように振り返ります。
それと言うのも、呼吸器をつけたその時点では、親である私どもが息子の人生を反面、諦めていたと言うことに他ならなかったからかも知れません。
そうした母親の私に東大小児科の先生方は、不治の病を背負ってしまった我が子と共に生きる積極さと、そして勇気を持つことの指針を傾けてくださいました。
先生方は、呼吸器に繋がった患者に散歩を敢行させたり、入浴をさせたりといった、より普通の生活に近い体験をさせ、それを実行させて下さいました。素人の側からすると、呼吸器を装着することが即ち、終末医療としての役割を果たすものとしての概念を根底に持っていたので、呼吸器を外しての外出や入浴が可能であることに、正直言って大きな不安と驚きと戸惑いがありました。
息子が五歳頃だったでしょうか。看護学校を卒業した新人看護婦さんが、看護婦として独り歩きを始めた頃、彼女が話してくれた印象深い言葉が思い出されます。
彼女は九州の看護学校を出て友人と共に上京すると小児科と内科に配属され、それぞれが日々の看護をする中で、二人はお互いの看護の在り方に疑問を唱えるようになりました。
内科の彼女の意見としては、呼吸器装着患者に入浴や外出は危険きわまりなく非常識であり、とんでもないことだと言い、小児科の彼女は入浴も外出もそれを当然の事だと受けとめていました。こうして、二人の医療と看護に対しての考え方は、配属された科によって大きな隔たりを作ったわけです。
昨今、医療関係者のみならず一般的にも“クオリティオブライフ”という言葉を声高らかに唄い挙げるようになりましたが、東大小児科は既に十五年前、これを実践していたわけで時代の先端を歩んでいたと言えるでしょう。
この長い間の実践は、呼吸器装着患者を親がひとりだけで屋外に連れ出したり、入浴も生活の一端としてごく当然の受けとめられ方で行われてきました。これは、とりもなおさず小児科に、呼吸器装着患者の入院の在り方に対する既成概念を打ち破る発想の転換という土壌があったのと、それを支持される先生方の存在が大きな影響を与えていたからなのでしょう。
そんな私たち親子の長期間の入院生活をまとめてみては?と、十年間書き綴った私の闘病日記の存在をご存知だった小林美由紀先生は、執拗に本を出版するよう勧められました。考えたあげく私は自分が文章を書くという能力が無いことを棚にあげ、話に乗ってしまったのです。
しかし、それに挑戦したのはいいけれど、これが遅々として進まず、息子が寝入った深夜の病室の傍らで十五年間を振り返りながら書くこと四年。いつのまにか歳月は経っていました。
一方で、息子にはコンピュータの画面に映し出された平仮名五十音から唯一、残された眼球運動を使って文字を選び出させ、意思の疎通を図らせようという大人達の思惑がありました。が、これは本人の頑ななまでの拒絶にあい、計画はあえなく沈没してしまいました。
ところが手段があったのです。音に敏感で音楽好きの息子のために、コンピュータ画面の五十音一つ一つに、ド・レ・ミと音階を付けることで興味を引きつけたのです。この瞬間から息子の眼は大きく見開き、瞼をクルクルと回し始めました。
つまり、“あ”を「ド」、“い”を「レ」、“う”を「ミ」としたのです。
こうして、なかなか筆の進まない私を後目に、文字で意志の伝達方法を頑として受け入れようとしなかった息子は、養護学校の担任の先生と一緒に中学一年の秋頃から音並べを始めたのです。
やがて平仮名五十音が映し出されるコンピュータから作曲の道具がキーボードに変わり、担任の先生が音を叩き出す聴音で曲を作る授業が始まり、本格的に曲がゆっくりと出来上がっていきました。
このことが文字を使って意志の伝達をさせることを小休止させ、音でそれを表現することに教育方針を変更させたのです。だからといって決して文字を習得させるのを諦めた訳ではなく、それは曲作りと並行して行われてもいました。
つまり、伝達方法を文字から音に変えて自己表現をし、それを果たすこと。それが息子に対するひとつの教育目標になったのです。
東大病院にも今春から「院内学級」が開級しました。それまでは障害が重くて通学が出来ない為の訪問教育で、息子は週に三時間しか授業が受けられず、教科学習が大幅に遅れていたことが、いつの間にか私の心に「教育」に対しての拘りを持たせ、焦りの色を色濃く落とさせていました。
しかし、担任の先生のとられたメロディーで息子の心の呟きを表現させ、作曲という手段を見出し引き出せて貰えたこと。それが私の学校教育という既成概念を取っ払わせ「教育とは・・・」を改めさせてくれました。
息子のCDが自費製作で出来上がり発売され、それから遅れること約一年。やっと書き終えた文章は『やっくんの瞳』と題されて岩波書店から六月十四日に発売されました。
当日の朝日新聞夕刊紙、全国版に掲載されたことで、「感動しました。何とか取材させて貰えないでしょうか。」というテレビ、ラジオ、雑誌などのマスコミ関係者から、異口同音の取材申し込みを受けました。が、既に放送済みのNHKラジオと朝日新聞以外は全て丁重にお断りしたのです。
息子が多くの方々から与えてもらった十五年間と、病室で大切な育みをもたらせた体験は、私たちの中でごく普通で、当然の生活の成り立ちとなっています。これがマスコミの手に依って興味本位でしかも、過度でセンセーショナルに取り挙げられることに懸念をもった事と、もう一方では、穏やかに生活している病室に取材で押し寄せられ、受ける自分達に大きなストレスがのしかかってくるであろうことに恐れを抱いたからでした。
小児科の先生方は、“クオリティ・オブ・ライフ”の旗を大袈裟に振りかざすことなく、呼吸器装着患者や多くの長期入院患者を見守り続けられました。お陰で私たちは入院生活を普通に近い営みとして日常生活化させ、これを送ることが出来ています。
本来、入院にはいろいろと制約がありますが、それに縛られることなく、小児科で入院生活を送れる患者と母親たちは、闘病の中にあって心の安らぎを感じられています。
私たち親子は、十五年前に検査入院の為の病院選びで、引き寄せられるように東大小児科を選びましたが、長期間を通してこの選択に間違いはなかったと思っています。
明日の命がどうなるのかも分からなかった息子は、CDで新しい活路を見出してもらい、私は思いもかけなかった本の出版を終え、それぞれの役割で親子が記録を残せました。
CDと本という形の裏には、小児科で出会った先生方や看護婦さん、そして多くの仲間達や支援して下さる方々に支えられ育ててもらわなかったならば、ここまで到底たどり着くことは出来なかったという思いがあります。ここに改めて、紙面をお借りしてお礼申し上げたいと思います。有り難うございました。
息子の存在は私ども夫婦を成長させ、感謝の気持ちを持ちながら日々を送れさせてくれています。
障害を持つ子とそれを抱える親の全てが、決して不幸ではないことの証明を息子は身を持って体験させてくれました。
多くの方々のお力添えで、色々なことが形成されてきました。これからは息子が二十歳になったときに、どう生きているかが大切であり、親子の今後のテーマでもあるように思います。
今までもそうだったように、息子が一つのことを成し遂げるには、多くの時間を必要とします。私たち親子が生きていく事は、こつこつと繰り返される糸紡ぎのようなものなのかも知れません。紡ぐ糸が何色で、どんな布に織りあがっていくか見当がつきませんが、でも私たちは何事もチャレンジしてみることから、いろいろなことが始まっていく事を体験してきました。描く夢の実現に向かってそれを求め、負担にならない程度にチャレンジを続けていきたいと十六年目をスタートした今、心新たに思うのです。